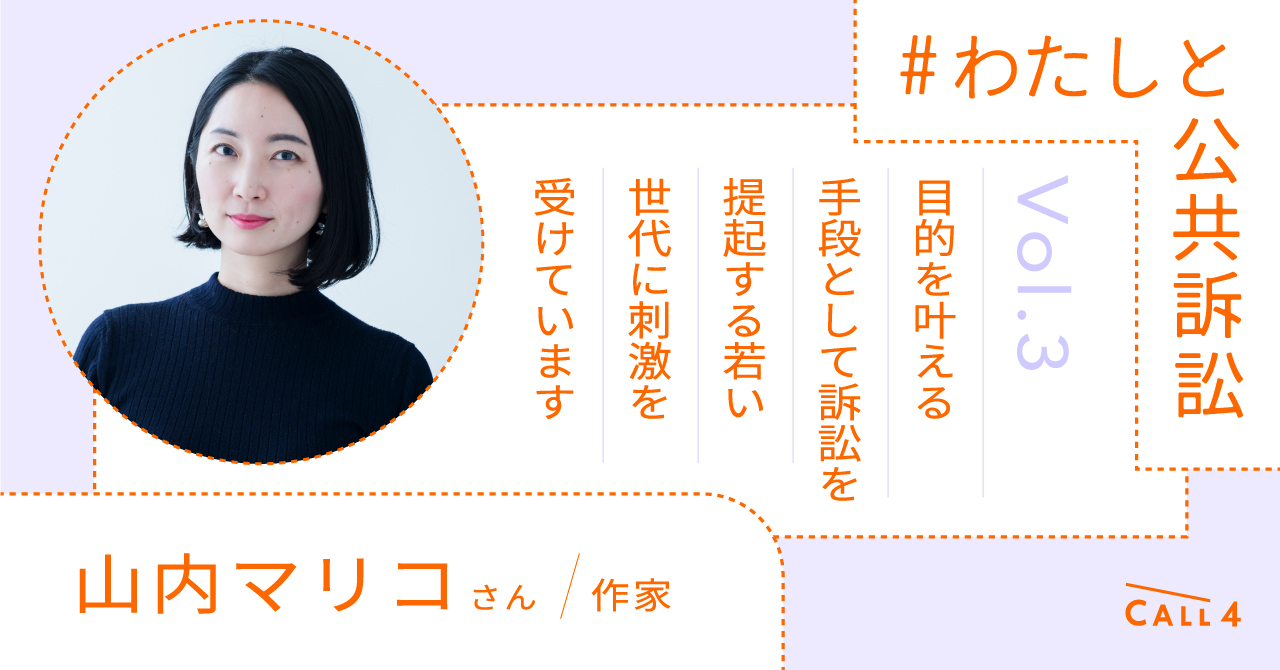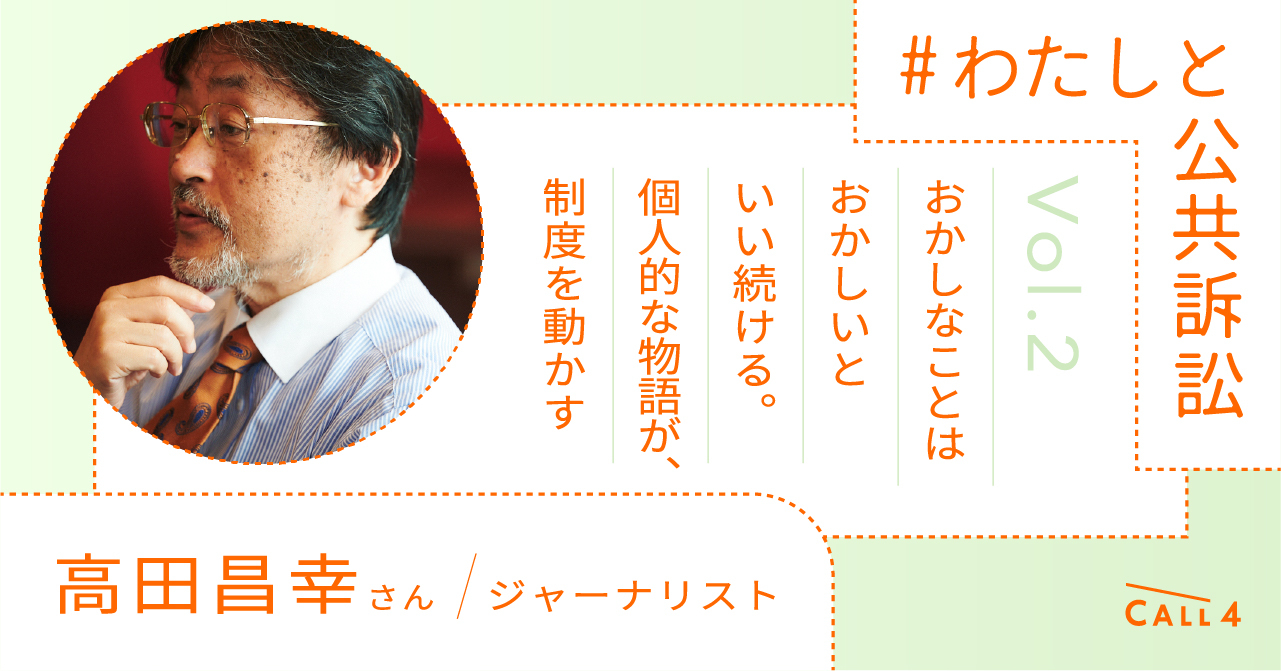当事者が関心を持っていると伝えるために傍聴に足を運んでいます

「人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟」の傍聴記や、「まんがで解説! 社会を変えた公共訴訟」シリーズなど、CALL4のサイトでもレポート漫画を通じてそれぞれの訴訟内容をわかりやすく伝えるコラムを連載中の漫画家の藤見よいこさん。
自身もミックスルーツの藤見さんは、当事者意識を持って「人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟」や「国籍法11条1項は違憲訴訟」などの経緯を見ているという。
普通に暮らしている人が、こういう目に遭っている
抽選に通るかどうかにわからないのに遠方の裁判所まで足を運ぶように、傍聴好きの人たちはすごく熱意がありますよね。傍聴ライターの高橋ユキさんが好きで、著作や記事なども読んでいましたが、法律に詳しくない私は記者やジャーナリストでない自分が法廷に行く意味があるのかと思っていたし、裁判所に対しては少し敷居の高さも感じていました。
初めての傍聴は、2024年春の「人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟」の第1回口頭弁論期日でした。ミックスルーツの友人たちと足を運んでいたので、当事者が関心を持っていることがパッと見でも伝わればよいな、と(笑)。
定員100名近い大法廷に傍聴希望者が170人以上も集まったので、抽選前から「当たったら誰が傍聴するか、より当事者性が強い人たちに入ってもらうのがよいのではないか」などと話していました。
私は抽選に外れてしまい、(傍聴できないことを)仕方ないと思っていたのですが、当たった妹や友人から「あなたが描かなければだめでしょう」「絶対に描きなさい」といわれて傍聴券を渡されて。自分が傍聴して、この問題を伝えなければと、そのときあらためて使命のようなものを感じたことを覚えています。
レイシャルプロファイリングについては、普通に暮らしている人がこういう目に遭っていることを伝えられればと、これまでも漫画で描いていましたが、第1回口頭弁論期日の意見陳述の冒頭で、原告でパキスタン系日本人のゼインさんが「この人、日本語上手いなと思った人は、この部屋にどのくらいいるでしょう」と話したときは、泣きそうになるほど感銘を受けました。


日常で起きている、無自覚な差別を描きたい
初傍聴で印象に残っているのは、周囲の人がすごくメモを取っていたことです。研究者や私のような漫画家とか、書くことや表現を仕事にしている人だけでなく、それぞれがこの問題を伝えよう、広めようとしている。そういう思いや力を感じました。
「ほんとにそんなことあるの?」「警察は治安維持の仕事をしているだけでしょ?」「(職務質問された人は)何か不審な挙動をしていたんじゃないの?」
レイシャルプロファイリングに対して、ネット上ではこうした声があがっています。でも、実際、スーツを着てオフィス街で仕事をしている私の家族が日中、東京の典型的なオフィス街で職務質問に遭っているんです。
経験の有無によって見える世界は違うし、一口にミックスルーツといっても、見た目でわかりやすい人もいれば、そうでない人もいます。
世の中には意図的に差別をする人もいるけれど、それよりもよかれと思っていったこと、やったことが相手を傷つけるマイクロアグレッション(無自覚な差別)のほうがよほど多いので、露骨な差別主義者のことより、日常で起きていることを描きたいと私は思っています。
私自身はレイシャルプロファイリングを受けてはいなくて、社会に対する違和感もあまり意識せずに生きてきました。そんな自分にとって衝撃的だったのが、2018年に起きた医大の不正入試問題です。
性差別によって合格ラインを操作したことについて、社会的地位のある少なからぬ人が「仕方ないこと」と済ませようとしている。そこからフェミニズム関係の本を読み始めて、その流れで出合ったのが、下地ローレンス吉孝さんの著書『「混血」と「日本人」―ハーフ・ダブル・ミックスの社会史』です。当事者のいろいろな話を読んで、自分だけじゃないんだなと、このとき初めて、個人的な体験が社会に接続するのを感じました。
訴訟が報道され、話題になることで、人の意識も変わっていく
たとえば日本人のパートナーがいても、同性というだけで定住者や配偶者ビザが認められなければ、異性愛者よりも不安定な状態で在留しなければなりません。社会で普通とされる人たちから外れるとされるマイノリティの人たちが受けている差別は、解決されるべきです。
それまでも、同性愛の人も結婚できればいいのにと、漠然と思っていましたが、今の社会はすごく不均衡です。そのうち変わる(同性婚が認められる)といいな、ではなく、法律として是正しないといけないと思ったのは「結婚の自由をすべての人に(通称:けじすべ)」訴訟を知ってからですね。
公共訴訟の最終目標は、法改正を通じて社会を変えることでしょう。ただ、「けじすべ」のように報道を通じて話題になることで、訴訟提起からこの6年で、人の意識はだいぶ変わっています。
まだ差別的な人もいるとはいえ、表立って同性愛者に差別的な言動を取ることは許されない雰囲気が醸成されたように、公共訴訟はそのプロセスも大事ではないかと思います。
「まんがで解説シリーズ」の第1回では「タトゥー裁判」を取り上げましたが、タトゥーと漫画は、世間でインモラルとされることもある、という共通項があります。この訴訟は、表現の自由という自分にとって関心のあるテーマだったので、捜査の経緯を知ったときは、警察は本当に怖いと思いました。
そもそも日本のエンタメは公権力を美化しすぎています。外国人への差別について考えると、公権力はラスボスのような存在なので、個人的にはその視点は無視はできないと考えています。
先ほども、世の中には露骨な差別よりもむしろマイクロアグレッションのほうが多いと話しましたが、3月末に刊行予定の『半分姉弟』はミックスルーツの姉弟のストーリーで、レイシャルプロファイリングや、彼女たちが日常で直面する葛藤を描いています。
連載開始まで時間がかかったり、自分でダメ出しをして納得がいくまで描き直したりもした思い入れの強い作品なので、多くの方に読んでいただけると嬉しいです。

CALL4は影響力のある公共訴訟をたくさん応援しているし、広い視野で社会にコミットしようとしているところがいいなと思います。
裁判についてはまだわからないことも多いですけど、期日の後、弁護団のみなさんが報告会で説明してくださるのを聞いて、なるほどと腑に落ちる感じです。今後も私にできることを通じて、訴訟やCALL4に協力していければと思っています。