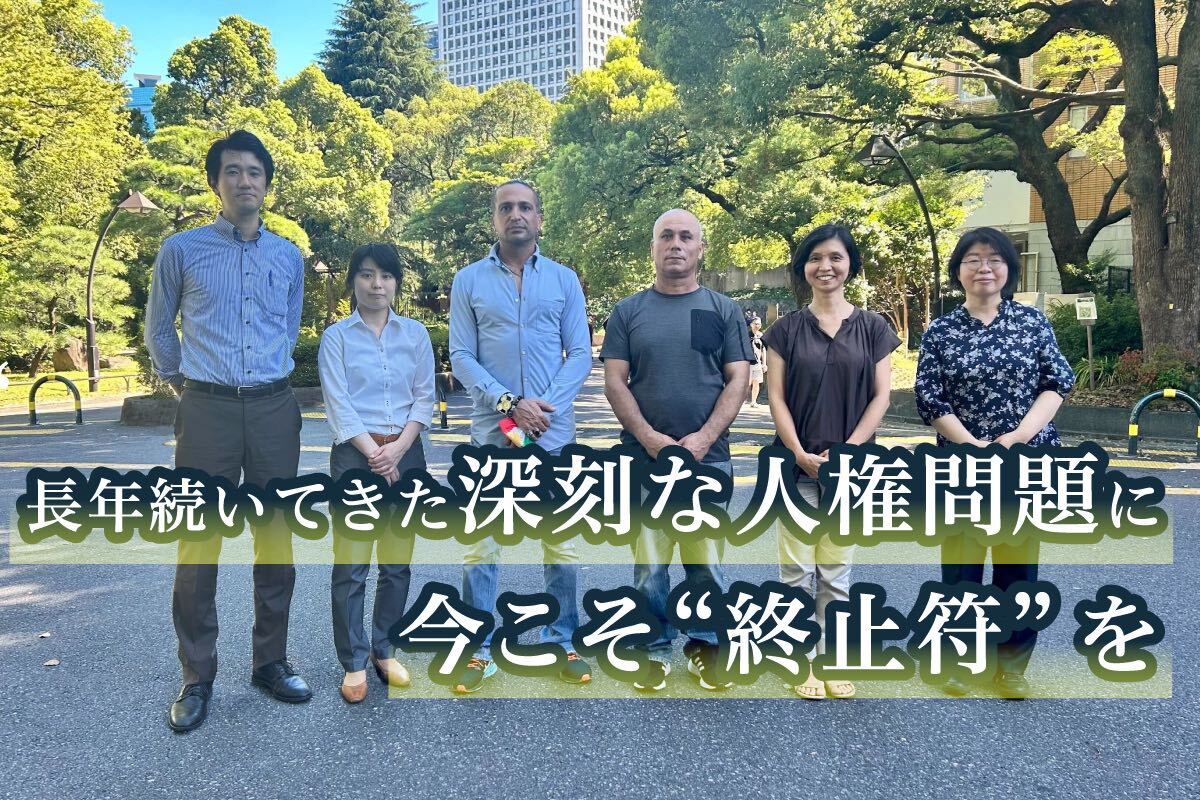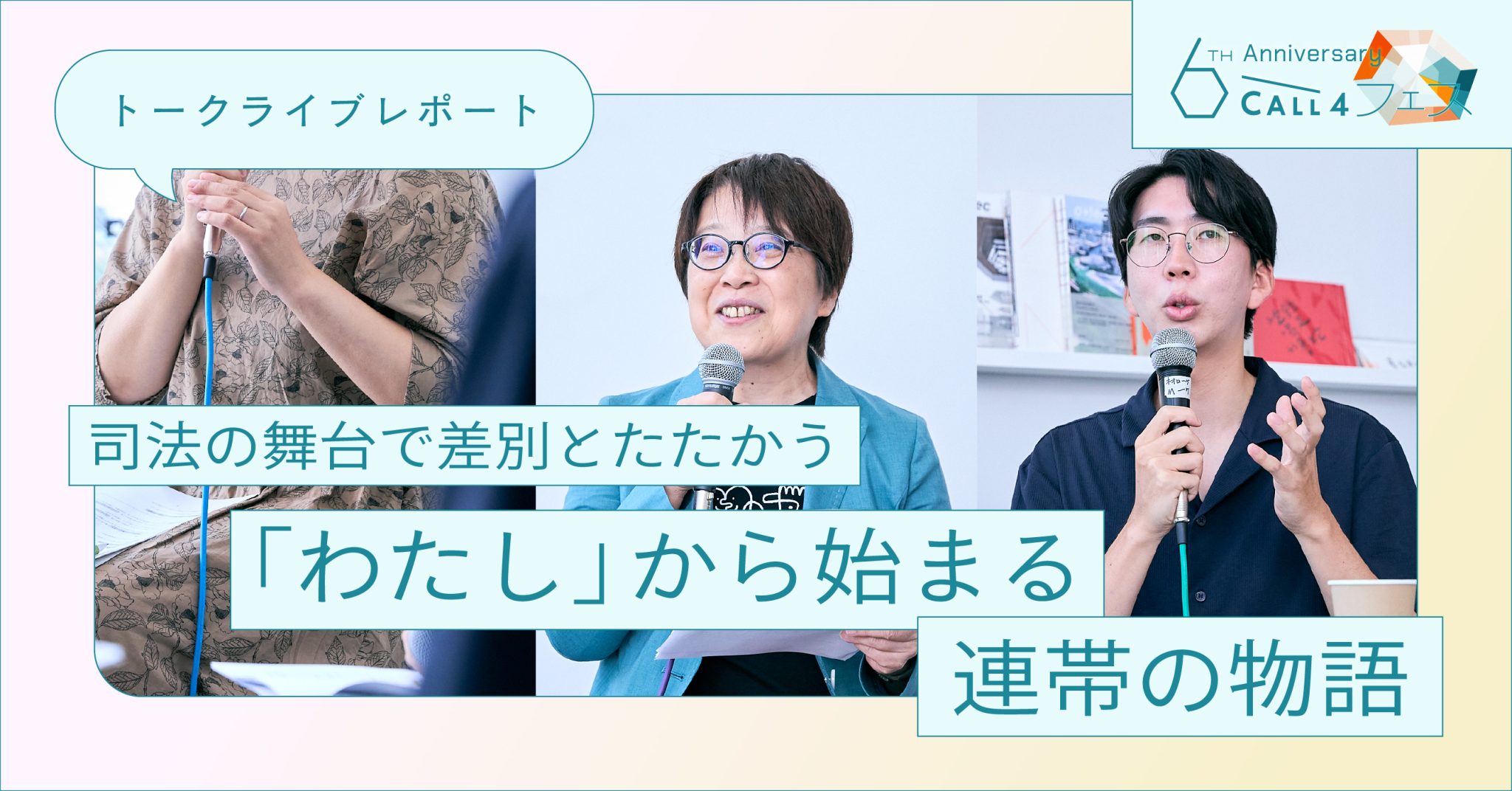集合知で乗り越える、公共訴訟・主張と立証の新展開
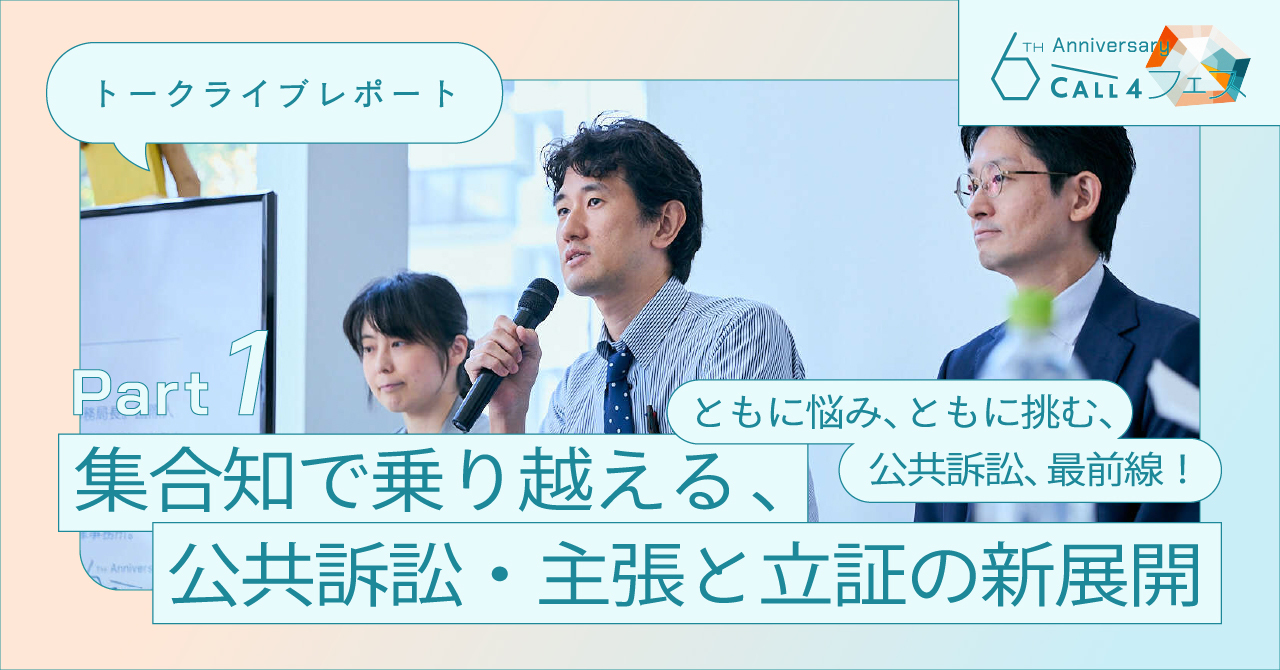
2025年9月27、28日に東京のSHIBAURA HOUSEで開催された6周年記念CALL4フェス。当日は公共訴訟に関心を寄せる多くの方々が、会場に足を運んでくださいました。
DAY1のタイトルは「ともに悩み、ともに挑む、公共訴訟、最前線!」。公共訴訟の最前線で奮闘する弁護士、公共訴訟の役割を社会に伝える担い手、そして原告の方々による3つのトークセッションの様子を3回に分けてレポートします。
Part1:「集合知で乗り越える、公共訴訟・主張と立証の新展開」
公共訴訟は身の回りで起きていて、社会全体にも関わる「おかしなこと」をなくすために提起されます。今の社会の当たり前に挑むことも少なくありません。訴訟を勝利へと導くため、これまでのたたかい方では突破できない壁を前に、弁護団はどのように主張立証を工夫するのか?
パート1では、画期的な判決を得たケースで代理人を務めた浦城知子弁護士、小川隆太郎弁護士、平 裕介弁護士に、訴訟を通じて実践したさまざまな工夫について、お話しいただきました。
浦城知子弁護士 2006年弁護士登録。外国人の権利擁護に取り組み、外国人関連の事件を多く受任。
小川隆太郎弁護士 2014年弁護士登録。NPO法人ヒューマンライツ・ナウ事務局長。人権問題や外国人関係の事件を受任。
平 裕介弁護士 2008年弁護士登録。主に行政訴訟・憲法訴訟に取り組み、ロースクールで9年間、専任教員を務めた(専門は行政法)。
MC:柬理美結(CALL4メンバー)

【国際人権法を活用して得た画期的判決①】「日本の入管収容は国際人権法違反」訴訟
最初の事例は、浦城弁護士と小川弁護士が代理人を務めた「日本の入管収容は国際人権法違反」訴訟です。原告の権利救済のため、国内法やこれまでの判例や議論だけではよい判決を得るのが難しい、その典型が入管収容の問題です。
ケース概要・訴訟提起の背景
「日本の入管収容は国際人権法違反」訴訟の原告2人は難民申請中で、それぞれ約15年、31年間在留していますが、在留資格のない状態にいます(年数は提訴当時)。日本の入管法は在留資格を失い、退去強制令書が出た人を(帰国するまで)無期限で収容できるとし、特に2016年から収容を厳格化しました。
先が見えない状態や長期収容に耐えられなくなった被収容者のあいだで、この時期、外に出るためにハンガーストライキ(以下、ハンスト)が広がりました。その背景の一つには、日本の難民認定率が国際的に見て極めて低いという問題があります。難民申請者は、本国に帰国すれば本国の政府等から迫害をうけるおそれがあるため帰国できないとして難民申請をしているところ、日本では国際基準から乖離した難民該当性の判断がなされており、そのため本来は難民として認定されるべき人までが認められず、不法滞在者として無期限収容の対象になってしまうのです。また、難民申請者ではなくても、日本で長年暮らすうちに日本で家庭を持つようになり、パートナーや子どものためにも帰国できないという人もいます。
つまり、入管の被収容者には、本国に帰りたくても帰ることができず、入管施設での無期限収容に耐えるしかない状況に置かれている人々が少なくないのです。人間らしい生活を送ることができない入管施設での無期限収容の中、肉体的・精神的な限界を迎え、人の命すら守られないというその非人道性に抗議するためにハンストという手段が取られたのでした。
ハンストという被収容者の抵抗を受け、入管は一時的に収容を解く仮放免を認めたものの、その期間はわずか2週間。その2週間のうちに体力を回復させて2週間後に出頭した被収容者を再収容するというショッキングな運用を適用しました。原告の2人も、この2週間仮放免を2回、3回繰り返されて鬱状態を発症したため、こうした状況を国連の恣意(しい)的拘禁作業部会に通報し、その後、訴訟を提起しました。
この訴訟で弁護団が正面から主張したのが、自由権規約9条という国際条約です。
「まず憲法と法律では当然、憲法が上位で、憲法違反の法律は無効です。憲法と条約では、並列、あるいは憲法が上ではないかという議論がありますが、少なくとも条約が法律より上位なの法規範であるということは判例通説なので、私たちは裁判所に、国際人権条約に反する入管法は無効だと宣言してほしいと要求しました」(小川弁護士)
自由権規約9条1項にある「何人も恣意的に逮捕され、または抑留されない」に着目した弁護団は、原告2人に対する収容は9条1項に違反すると考え、恣意的とはどういうことか、この条文の解釈を徹底的に検討し、法廷でも熱く論じたといいます。
「①目的の合理性、②収容の必要性、③その必要性と本人たちが受ける利益不利益のバランス比例性(均衡)は取れているか――この3つの要件を満たさなければ、その収容は恣意的で、条約違反だという解釈・主張を展開しました」(浦城弁護士)
また、弁護団は、自由権規約9条1項が求める3要件を満たしていないにも関わらず、退去強制令書が出た人は無期限に収容して構わないという運用を可能にしている日本の入管法そのものが自由権規約9条に違反していると主張しました。
一審判決について
裁判所は3要件を満たさない拘禁は、恣意的であると認めました。その上で、入管法自体を自由権規約9条1項に適合的に解釈し、入管法52条5項は、3要件を満たしていないと収容してはいけないと規定していると読み込むことで、「自由権規約には反していないと解釈する余地がある」として、入管法そのものが自由権規約9条1項に違反するものではないとしました。
そして、原告2名が最後、それぞれ2週間仮放免の後の再収容を2回、3回繰り返されたことは、自由権規約9条1項と入管法に反し違法であるとして、損害賠償が認められました。
しかし、残念ながら裁判所は2016年から2019年まで続いた長期収容については、違法としませんでした。
今回の判決を導いた要因として、浦城弁護士と小川弁護士が挙げたのは、①主張を自由権規約違反に絞ったこと、②国連恣意的拘禁作業部会(WGAD)におこなった個人通報に対し、意見書をもらえたことの2点です。
①退路を断って、自由権規約の主張に絞る
まず、主張を自由権規約違反のみに絞ったことについて、浦城弁護士は、「これまで入管収容の違法を認める判例はなかったことから、論点を複数にすると裁判所は憲法や国内法(入管法)に流れてしまう可能性があったので、この解釈を適用してもらうことを主張し、法廷でも複数回、意見陳述をおこないました」と説明。
小川弁護士も、「国連の解釈書にも『国内法に適合していても、自由権規約違反になりうる』とはっきり書かれているので、入管法で合法だとしても、自由権規約で判断すべきだと裁判所に訴えました。また、身体の自由は原則で、必要性・合理性・比例性がないのに外国人だから無期限に収容できるのはおかしいことだという国際人権法の学者がたくさんおられるので、複数の意見書を、裁判所に提出しました」と、主張を自由権規約に絞ったことを強調しました。
②国連恣意的拘禁作業部会(WGAD)への個人通報
WGADは、国連人権理事会が設置した特別手続で、恣意的な拘禁がされていないか、各国を訪問したり、調査研究や個人通報手続をしたりする機関です。今回の訴訟は、WGADへの個人通報が認められ、入管問題では初めて意見書をもらうことができたケースとなりました。

【国際人権法を活用して得た画期的判決②】赤ちゃん取り違え被害者に「出自を知る権利を」訴訟
2つ目の事例は、小川弁護士が代理人を務めた、赤ちゃん取り違え被害者に「出自を知る権利を」訴訟です。
ケース概要・訴訟提起の背景
都内の都立産院が赤ちゃんを取り違えたため、実の親と引き離された原告は、取り違えに対し、東京都を相手に訴訟を提起し、勝訴します。しかし、その裁判で損害賠償は認められましたが、敗訴後も東京都は生みの親の調査は実施してくれませんでした。その後、自分自身で生みの親を知るため、区に情報開示・調査を請求したものの黒塗り開示だったため、都に調査協力を求めたものの、それすら拒否されたことから、出自を知る権利を根拠に、都を相手に調査と損害賠償を求める訴訟を提起。2025年4月の判決で、裁判所は都に調査を命じました(都は控訴せず判決は確定)。
先例のない訴訟で、主張をどう組み立てたか
赤ちゃんの取り違えというまれなケースについて、国内法自体が整備されていないなか、弁護団はどのように主張立証を組み立てることで調査義務を認めさせたのか。小川弁護士は、次のように話しました。
「生みの母親のことを知りたくて訴訟を提起したのに『すでに賠償金を払っている』と求めに応じない都の姿勢によって、原告への人権侵害が続いていました。自由権規約には、人権侵害を受けた場合、効果的な救済が必要という概念があることから、賠償金以外の救済を求める方法を調べて適用したのが出自を知る権利です。出自を知る権利や家族が結合する権利の侵害は、子どもの権利条約や自由権規約といった国際人権条約に違反しているので、加害者である都には損害賠償義務だけではなく、謝罪や調査により被害者に効果的救済を与える義務があるという主張です。最終的に裁判所は、契約上の義務の解釈において国際人権条約を間接的に適用し、出自を知る権利を踏まえ、都に調査を命じました」
国際条約の活用法について――今後の判例につなげるために
日本が批准していない国際人権条約には使えない、国連に対し個別のケースで意見書まで出る通報ができるのは、日本では今のところWGADのみではあるなど、訴訟に国際人権法を活用するには、まだハードルもありますが、それでも2つの事例には、公共訴訟において参考になることも少なくありません。
「先例が少ないことは、それだけ国際条約には開拓の余地があるということです。個人通報制度は条約ごとにあるので、裁判所に新しい判例をつくってもらうためにも、海外の判例や人権に関わる条約機関の判断はぜひ活用してほしいです」と浦城弁護士はいいます。
「出自を知る権利を」訴訟で、ヨーロッパ人権裁判所の判例を複数出した小川弁護士も、「自分のリーガルマインドを信じて、これやっぱりおかしいなって思って、国内法の判例や、国内法ではどうも救済しきれないなというときに、海外に目を向けて欲しいなと思うんですね。ヨーロッパでも赤ちゃんの取り違えや、戦争によって親子が引き離されることはあり、日本はヨーロッパ人権条約を批准していませんが、ヨーロッパ人権裁判所における人権ベースで考えるとこうなる、という理屈付け(ラショナーレ)自体は普遍性を有するので、日本の裁判官にも通じると思います」と続けました。
では、国際人権法について、どうやって調べるのか。小川弁護士は、「私は申惠丰(シン・ヘボン)先生、近藤敦先生による国際人権法・人権法の教科書を参考にしています。ヨーロッパ人権裁判所のウェブサイトでは、条文やテーマごとに判例をまとめているケースローガイドがあるので、そこで関連する訴訟に当たるとよいと思います」と、具体的な話を挙げてくださいました。

【憲法を活用して得た画期的判決】『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟
3つ目の事例は、平 裕介弁護士が代理人を務めた、『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟です。
ケース概要・訴訟提起の背景
映画『宮本から君へ』への制作にあたり、映画会社が申請し、内定していた助成金が、出演者の一人が薬物事件で逮捕されたことを理由に、公益性の観点から、最終的に交付しないこととする不交付決定(行政処分)がされました。
これに対し、映画制作会社である原告は「表現の自由」(憲法21条1項)の観点等から本件不交付決定には行政裁量の逸脱・濫用があるとして、本件不交付決定の取消訴訟を提起。地裁勝訴、高裁敗訴を経て、最高裁で逆転勝訴を得ました。
助成金や補助金の給付は、とりわけ行政裁量が広いとされる場合が多い分野だと、平弁護士はいいます。
「行政は、助成金や補助金について、いきなり申請を拒否する行政処分を行う前に、まずはその申請の取り下げを要請する行政指導をおこないます。欧米と違い、日本では行政の指導・指示には従うべきと考える人が多く、こうした自粛要請が効くんです。ただ、原告代表者の河村光庸さんは、“表現の自由”の観点からこのような要請や不交付決定を問題視し、提訴しました」
この事例で、行政側は、「このまま助成金を交付すれば、薬物OKという印象をもたらし、それは国民の理解を得られないだろうから、“公益”の観点から不交付とする」といういい分を主張していました。しかし、“公益”という概念は非常に広く、公益性を持ち出せば、すべて行政(国家権力)の都合で判断されかねず、助成金や補助金への依存度が高い独立系映画の製作者が不交付を示唆されたり、抽象的な“公益”による不交付決定を受けることになれば、時の国家権力に意向に沿うような忖度(そんたく)せざるを得なくなるのではないか、と平弁護士はいいます。
「原告の河村さんの会社は『新聞記者』『パンケーキを毒見する』『妖怪の孫』と、それぞれ安倍晋三元首相、菅義偉元首相、安倍首相の祖父の岸信介元首相を批判する映画を製作しています。そういう会社にはできるだけ助成金を出したくないというのが行政の意向であることが予想されるわけで、『宮本から君へ』には政治性は全くないのに、出演俳優の不祥事が起きたことで、いわば江戸の仇を長崎で討とうと、助成金を交付しないといい出す。このような印象を映画業界全体に植え付けることもできるわけで、もしこの裁判で負けていたら、映画製作者側による国への忖度はより強くなっていたと思います。そして、科研費等の補助金に依存することが少なくない研究者の学問の自由などについても同様のことがいえ、国への忖度や萎縮効果が生じる危険がありました」
判決について――地裁、高裁、最高裁
高裁で負けて最高裁で逆転勝訴する確率は、統計上、1%未満です。弁護士がいう「高裁の壁」を覆した画期的判決について、平弁護士はこう解説しました。
「専門家の判断で助成対象に内定したことを重視した一審に対し、高裁では不合理な一般論を述べられたことなどから敗訴しましたが、最高裁は、芸術的観点以外の公益の重要性と公益が害される具体的な危険が認められなければ、そのような公益を重視することはできない、つまり行政側が何でも“公益”といえば裁量の範囲内になり適法となるわけではないと、裁量権の逸脱・濫用の違法性を認める判決を出してくれました」
「日本の入管収容は国際人権法違反」訴訟で、自由権規約9条1項に照らし、入管法の一部違法性が認められたように、この事例も、行政事件訴訟法30条の裁量権逸脱・濫用に憲法21条1項(表現の自由)の趣旨という上位法を活用した点は共通する、と平弁護士はいいます。
また、コロナ給付の対象から性風俗事業者を除外した、給付金行政における行政裁量の問題に関し、憲法22条1項(職業選択の自由)などを主張し、残念ながら最高裁で敗訴した別件の「セックスワークにも給付金を」訴訟について、「研究者やネットメディアの中には、宮川美津子裁判官が出した違憲という意見を好意的に受け止める声が聞かれました。この意見は今後の参考になると思うので、みなさんぜひ、反対意見にも着目してください」と付け加えました。
主張立証のためのさまざまな取り組み
弁護団の方々は他領域の知見も積極的に取り入れ、主張立証レベルでさまざまな工夫をしながら、画期的判決を導いています。そのひとつが世論調査で事実を可視化するサンプリング調査やアンケート調査です。
CALL4掲載ケース「人種差別的な職務質問をやめさせよう!」訴訟や前述の「セックスワークにも給付金を」訴訟では、弁護団はリサーチ会社に調査を依頼しました。調査では、外国籍者は日本国籍者の5.6倍の確率で職務質問を受けていること、性風俗事業者にもコロナ給付金を出すべきという人は反対する人の2倍いたというデータが出ています。こうした結果は、証拠資料として裁判所に提出されています。
それぞれの訴訟で代理人を務めた浦城弁護士と平弁護士は、調査にはかなり費用がかかるので、普通の訴訟ではできないが、支援者の方からのCALL4を通じた寄付によって大規模な調査を実現できたと口を揃えました。
また、被害を立証するためには、その分野の第一線で活躍する専門家の協力を得て意見書を出すこと、専門家とつながりを持つために学会や研究会に参加することなども大切だといいます。

多くの方が話に関心を寄せてくださったことを伝えるように、時間ギリギリまで会場から質問が重ねられたトークセッションパート1。冒頭のあいさつで、CALL4の谷口太規共同代表が話したように、最高裁での違憲判決をはじめとする画期的判決は、さまざまな人が努力をして、新しいアイデアを持ち込み、国内外の他の判例や学説を参照にするなど、粘り強い努力の積み重ねの先に生まれるものであることが、弁護士の方々の話からあらためて伝わってくる――そんなセッションでした。