司法を舞台に差別とたたかう 〜「わたし」から始まる連帯の物語〜
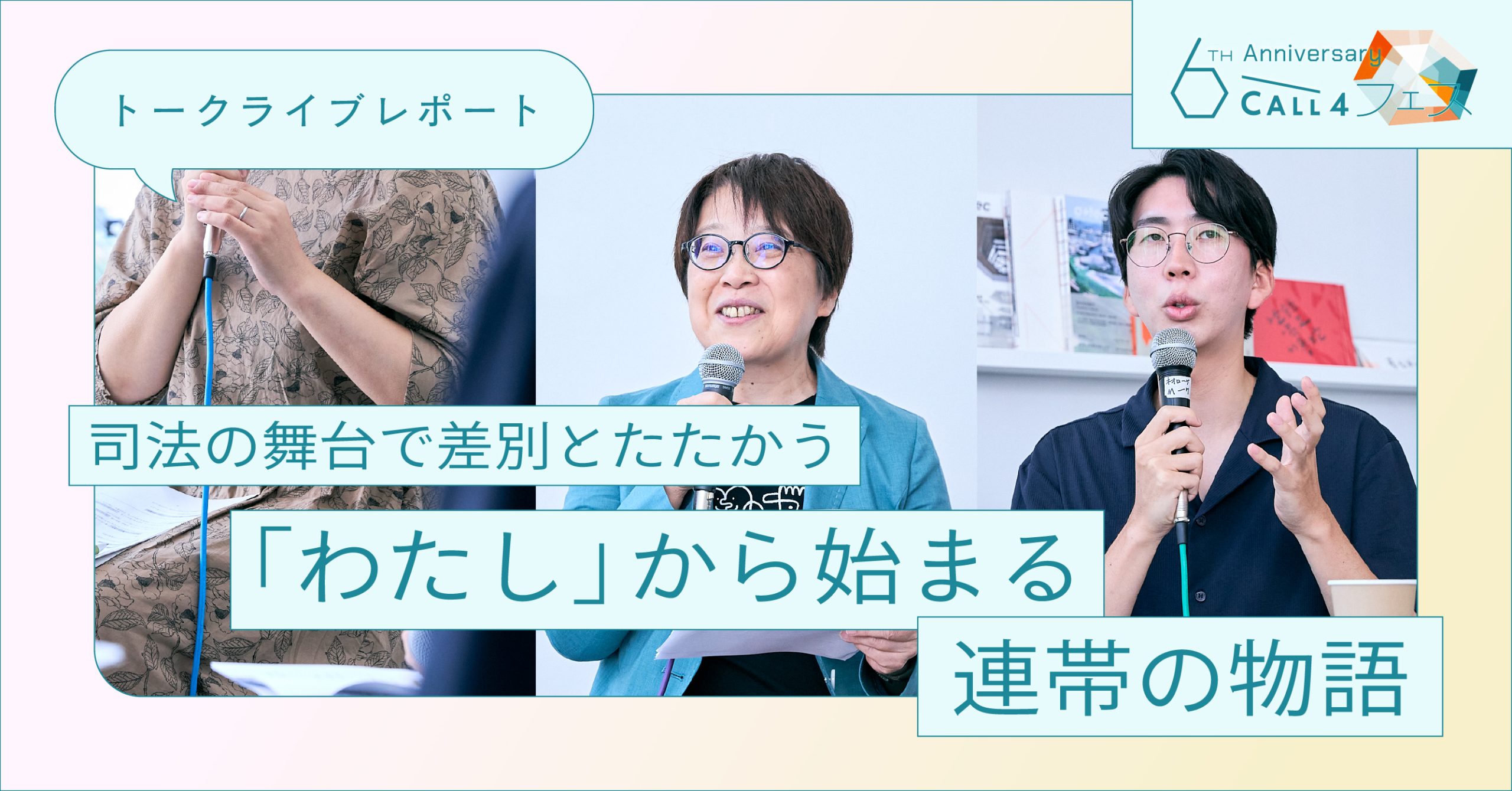
はじめに
想像してみてください。結婚したいと思っても、できない人たちのことを。
ただその職業を選んだ、という理由だけで、苦しいときに国から補助金を受けられない人たちのことを。
彼らのことを想像したときに浮かんだ言葉を、どこでもいいので書き留めてみてください。
この記事を読んだ後、あなたの言葉は、心はどう変化するのか——
国から「本質的に不健全」な職業だとして持続化給付金の対象外とされた性風俗業を営むFU-KENさん、愛する人との結婚が認められずに婚姻届を不受理とされた鳩貝さん——声をあげたふたりは決して特別なひとではありません。
あなたと同じ、この社会に生きるたったひとりの個人です。
これは、ふたりの「わたし」が語る、差別的な制度や社会構造とたたかう物語。
ふたりの原告の「わたし」から始まる連帯の物語をお楽しみください。

登壇者:
鳩貝啓美さん(結婚の自由をすべての人に訴訟・原告)
FU-KENさん(「セックスワークにも給付金を」訴訟・原告)
MC:
松岡宗嗣さん(ライター・一般社団法人fair代表理事)
不安や怖さはあった。それでも立ち上がる「責任」がある
松岡宗嗣さん(以下、松岡):
私にとって「国を相手どってたたかう」ということは、「大それたこと」で「想像もつかないようなこと」だとずっと思っていました。でも、実際に傍聴をしてみると実は、かけがえのない生活のこと、たとえば病院での手続や不動産を借りることとか、あるいは何かサービスを提供することとか、身近なことでもあるんですよね。
訴訟の原告になるときの不安と同時に、どういう感覚だったのかということをお聞かせいただけますか。
鳩貝啓美さん(以下、鳩貝):
東京一次訴訟(筆者注:結婚の自由をすべての人に訴訟)の応援をしていた頃も、なるべくリアルな姿を伝えたいという気持ちがあり、名前や顔は出す方針だったのですが、メディアの注目が予想以上に集まったことに大変なプレッシャーは感じました。特に、カミングアウトを大々的にすることに伴う反響や影響がどうなるかわからないという怖さがありました。
2年後に自分たちが原告になる時も同じ不安というか怖さはあったんですけど、立ち上がること自体には迷いはなかったかなと思うんです。
私には色々な人の声を伝える責任がある。そんな気持ちになっていたんですね。
30代の頃から、セクシュアリティに悩む人のための相談の場を運営していて、今ではレインボーコミュニティcoLLaboという形になっています。そこに次から次へと若い新しい人が来るんだけど、悩む内容は一緒だったんです。そこにすごくやるせなさを感じていたんですね。でもどうすれば社会が変わるかはわからない。
「社会を変えなきゃ」と思っていたときに、戸籍上の同性どうしが結婚できるようになるっていうことは、本当に大きな可能性だって信じられたことが立ち上がる上での迷いをなくしてくれました。
私自身が同性愛であることに気付いたのは、10歳の時でした。それを受け入れられるまでに18年くらいかかっちゃって。1970年代〜80年代というのは、今以上に同性愛への偏見もひどいもので、差別的な情報も溢れていました。「異常だ」とか「病気だ」という言葉を素直に受け取って、誰にも相談できずに、私みたいな人間は世界に独りぼっちだと思っていたんです。10代20代っていうのは、人と交わって自分を見つけていく、とても大切な人生の段階だと思うんですけれど、その時期に、同性愛者だっていうことを知られないように、人と距離を置きながら生きてきたんです。後になって『私だけじゃなかったんだ』と気づくんですけど、これってすごくひどいことですよね。こういうことを若い世代に繰り返してはならない、という意味で責任というものを感じていました。
松岡:
個人のストーリーの中に、『同じ当事者と共通している課題なのかな』『次の世代にとっても同じ高いハードルであり続けるんじゃないか』といった社会的な視点も入ってきて、『何かできることないかな』の選択肢の一つに訴訟というものが入ってきたのかもしれないですね。

同性どうしで結婚をしたい当事者が、「国会がいつまでも”同性カップルが結婚ができるための法律”をつくらないのは、憲法上の人権を侵害し、違法だから国は賠償すべき」と主張している訴訟です。
現在、30人以上の原告と約80人の弁護士が、全国5か所の裁判所で6つの訴訟を起こしています。この訴訟では、同性カップルが婚姻制度を利用できない民法や戸籍法は、憲法14条が禁じる不当な差別的扱いをするものであり、憲法24条が保障する婚姻の自由を不当に侵害し、24条2項の適合性を欠くものなどととして、制度改正を訴えています。
(※鳩貝さんは東京地裁に提起された二つ目の訴訟の原告であり、以下では鳩貝さんが原告を務めている訴訟を「東京二次」と呼びます)
知らないことだらけ、不安だらけ、バッシングだらけ。それでも、私が私に貼り付けたレッテルとたたかいたかった
FU-KENさん(以下、FU-KEN):
私は、元々社会問題に対してもそんなに関心があったわけではありませんでした。10代の頃から風俗のキャストとして働いていて、その後独立して自分のお店を持って、というだけで。そもそも、社会の授業で習うような『三権分立』とかも、訴訟を始めるまでは全くわかっていなかったんです。
コロナ禍で店の休業を決めたとき、キャストからはお店を開けてほしい、お金がなくて苦しい、というとても切実な声があがりました。でも店を開けると世間からバッシングを受けるし、キャストがコロナに感染するかもしれない。ギリギリの状態の中で、国から持続化給付金の対象から性風俗業者だけは除外します、と言われた時に、ものすごくショックを受けました。
これって差別じゃないかなという疑問から、色々なことを調べて、この社会の成り立ちや自分たちの立場の扱われ方を改めて知りました。だから、「何も知らなさすぎて不安しかなかった」という感じですね。
世間からの夜の街バッシングがありましたし、訴訟に対しては同業者からの批判の声もありました。色々なバッシングもありつつ、さらに公権力という…すごい権力を持っているらしいものに立ち向かわなければいけないこともとても不安でした。公務員のきょうだいに嫌がらせをされるんじゃないかとか。自分が性風俗の仕事をしているということを彼らに初めて打ち明けたりとかもしました。
あらゆる方向からの語り尽くせないほどの不安があったんですが、それを超える『おかしい』という気持ちがあったんだと、今振り返ると思いますね。
松岡:
最初に『訴訟を起こす』という方法が思い浮かんだんですか?
FU-KEN:
一番に思い浮かんだのは裁判でした。でも、ネットで調べても、勝率は低いしお金も時間もとんでもなくかかるっていう情報しか出てきませんでした。
裁判をする前に『政治に働きかけた方がいい』という情報が出てきたので、セックスワーク従事者の権利について活動している団体の方の支援を受けつつ、まずは中小企業庁に陳情書を提出しに行きました。
でも、そこでは漠然と「国民の理解を得られにくいので対象にはできないです」と繰り返されるだけ。何も変わらなさそうだと思いました。
『性風俗事業者』自体もとても少ないですし、多くの方の署名や賛同を集められるかというとそうではなく、一方で政治を変えるためには数が必要だったので、ハードルは高くても、裁判をしたいと思いました。学者さんや弁護士さんの書いていることを調べていたときに、憲法学者の木村草太さんがSNSで『憲法訴訟は1人でもたたかえる』と書いていらっしゃったんです。政治では有耶無耶にされることも、裁判ではきっちりたたかわせてくれるし、結論も出してくれるんだと思ってたたかうことを決めました。
松岡:
コロナ禍の時、生活が苦しくなったことによって政治に関心を持つようになった、という話は特に周りのフリーランスの人たちからたくさん聞きました。そこから、特に政治の網目から取りこぼされがちな人に対して共感の声を上げる人が増えたような印象があります。
でもそこからさらに訴訟を起こすには、また違う葛藤やエネルギーがあったんじゃないかなと思うんですが、どういう力が訴訟を起こすことにつながったのか、そういう出来事だったり印象的だったことはありますか?
FU-KEN:
給付金から性風俗業が除外された時に本当にショックを受けて、なんで自分でも国の決定にこんなにショックを受けるんだろう?と思いました。
もちろんお金が必要だった、という面もありました。
でも振り返ってみて、自分も含めた同業者の中には、『俺たち/私たちはそういう職業を選んだじゃないか』『世間に認められる職業とは別に思っていないよ』という『アングラのプライド』みたいなものがあると思うんですね。
『国から助けてもらおうなんて思ってないよ』というプライドはすごくわかるし、かっこいいとすら思っていました。風俗嬢になり、その後経営者になって、すごくずるいことをしている、何か大事なものと引き換えにお金を手にしているんじゃないか、という気持ちがありました。
自分の中にあったのは、結婚や子供、恋人すらも望んじゃいけないんじゃないか、ということですね。自分自身で性風俗に対するレッテルを貼っていたんだと思うんです。
でも、そのレッテルを国から貼られるっていうのはわけが違って、それもショックの原因だったのだと思います。私の中のモヤモヤの決着をつけるためにもやらなければならない訴訟だったなと思いました。
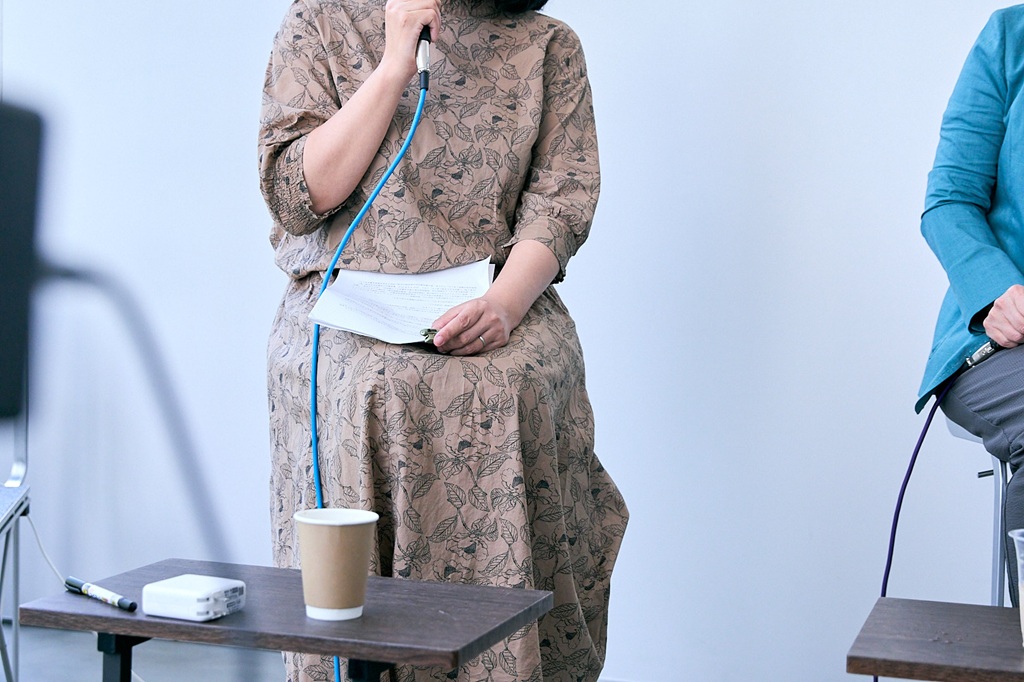
無店舗型ファッションヘルス(いわゆる「デリヘル」)として風営法上の届出をしている事業者が原告となり、性風俗関連特殊営業が、「国民の理解を得られない」として、新型コロナウイルス禍の下での給付金(持続化給付金・家賃支援給付金)の対象から外されたことについて、国を訴えました。
この訴訟では、性風俗店を給付金の対象外とした規定は職業差別であり、「法の下の平等」(憲法14条1項)に違反すると主張しました。しかし、2025年6月16日、最高裁は上告棄却判決を言い渡し、敗訴判決が確定しました。このとき、宮川裁判長のみが原告側の主張に呼応する反対意見を書きました。
批判する人たちの気持ちもわかる。それでも社会を、法律を、価値観を変えるチャンスだと思った
松岡:
鳩貝さんも、訴訟を起こすというのは大きなハードルだったと思うんですね。その時に何が力になったのかというのを、お話しいただければと思います。
鳩貝:
同性婚についての議論自体、始まったのはごく最近で、海外で同性婚ができるようになったらしいけど、日本ではそんなのできるはずがないよ、と私自身思っていました。『結婚したい』って思うこと自体が、選択肢になかったんです。
特にフェミニズムの力を借りながら自分たちの生き方を模索してきた世代の女性たちのなかで、「女性ジェンダーに対する抑圧の原因は、結婚や家庭生活にある、だからそもそも結婚制度自体を壊したほうがいい」みたいな考え方もあり、私はそこで思考停止してしまっていました。国際的な人権を獲得していこうという動きがある中で、それがどういう意味を持つのかというのをしっかり考えられずにきていたなぁという、そういうことに気づけたことが、大きい部分なのかなと思います。
松岡:
結婚制度自体がそもそも女性に対する抑圧として機能しているのだから、そもそも結婚制度自体をなくしたほうがいいんじゃないか、というのがフェミニズムの考え方の一つにあるんですね。これも一つの方向性だと思います。
ただ、目の前の生活の困難を解消するために婚姻制度があるのだから、それを平等に使えるようにすべきだ、という請求は並列してできるのではないか、というのはこの訴訟の重要な部分かなと思います。
お二人の訴訟提起に対しては、それぞれバッシングがあったと思いますが、どのように感じられましたか。
鳩貝:
「目立たないでくれ」、「静かにやってるんだから」という声をあげる方からすると、立ちあがろうとする動きによって、(同性愛者が目立ってしまうことで)「攻撃されるんじゃないか」という脅威を感じる、ということだと思います。その点については想像できないこともないです。
FU-KEN:
訴訟に反対する同業者の気持ちも、わからないではないです。でも、コロナ禍だったからこそ、こういう助成金から性風俗事業者が除外されているのを知れたという側面があります。これまでも除外され続けていたけれど、興味がなかったから知らなかったんですね。
今立ち上がらなかったら次の機会はないかもしれない。今こそ声を上げるチャンスなんじゃないかと思いました。
除外された理由について個人的に調べていたときに、風営法という性風俗事業者をひとくくりにしている法律に出会いました。風営法に従うことに疑問はなかったんですが、その法律自体がそもそもおかしかったんだなということに気がつきました。
店舗型の風俗店は新たに作れないし、大規模な改装もできない、という法律になっていたんです、店舗型のお店は火災対策すらできないんですよね。
働く人たちの安全を考えた法律ではないし、現実に即した法律でもないということを感じました。裁判が直接的に風営法の改善に役立つのかというのはわからなかったんですけれども、裁判の中でそこにスポットが当たるチャンスかな、とは思っていました。

「わたし」の苦しみや憤りは「社会」から切り離せないもの
松岡:
実際に裁判をたたかってみて、いかがでしたか。
鳩貝:
提訴をする記者会見から始まって、今日に至るまで、同じような立場の方々の前で話す機会や記者会見、メディアを通じての発信もありました。
ただ記憶に残っているのは、提訴してすぐの時期にパートナーの河智(さん)の病気がわかりまして、入院して手術するってことになって、ストレスを感じる状況に追い込んでしまったな、原告になろうなんて言わなきゃよかった、という後悔が発生しました。
一方、入院手続きの中で、やっぱり同性カップルは社会の中でパートナーとして認めてもらうためにこんなに手続が必要でこんなに苦労してっていうエピソードがたくさん出てきてしまって、これは裁判で訴えなきゃいけないなぁ、ともなりました(笑)。
スタート地点としてはそんな両面の気持ちがありましたね。
そして、裁判をしているので困難を中心に話さなきゃいけない役回りでもありますよね。でも、私の365日の大半は、同性愛者である自分を受容して、いきいきとアクティブに、パートナーと幸せな、ほんのりとした時間も送っているっていうギャップも感じていました。
松岡:
訴訟をたたかうときには、意見陳述をはじめ、戦略的に『かわいそうな私』を見せていかなければならない部分もありますよね。でも、別にずっとかわいそうと思ってほしいわけでもないし、かわいそうな存在でもないしっていう葛藤もありますよね。
鳩貝:
同性愛者の自分を受容することができた28歳の頃から、子供の頃の苦しみもレズビアンとしての試行錯誤も含めて、レズビアンとしての人生をすごく前向きにやってきたと思っています。
けれど、意見陳述をする時に生い立ちとか、どのような経験をしてきて訴えるに至ったかっていうところを振り返っていく作業があって、思っていた以上に苦しいし、しんどかったです。
陳述書を書きながらパソコンに向かってずっと泣いていました。
心の奥底から小さな自分や、孤独を感じていた10代の自分が語りかけてきて、全ての意味においては癒されてはいないんだろうと思いました。現代の若い方でも、似たような思いを抱えている方がいっぱいいるので、改めて現在進行形の問題だと感じます。
自分の中から始まって、周りの人たちを通じて「社会の問題だ」と感じて、悲しみも怒りも大きくなっていく、そういうプロセスだったと思います。
FU-KEN:
どうやったら国を訴えられるんだろうと、色々な弁護士事務所に相談に行っていました。そこではやっぱり、はっきりとした答えはもらえず、「いくらお金がかかるんですか」とか、「勝つ可能性はありますか」とか聞いても、「どうなんでしょうねぇ」みたいなことしか返ってこないし、おそらく本当に訴えるとは思われていないんだろうなって思いました。
でも、そんな中で、弁護団長の平弁護士の書かれている、コロナ禍における芸術イベントの損失と補償のあり方関する解説記事を見つけたんです。この人に一度相談しようと思い、実際に相談したところからCALL4さんとつながり、そしてクラウドファンディングで支援をいただくという案をいただきました。お金の面でも、手続の面でも、弁護士さんを見つけるという面でも、そこが大きなターニングポイントでした。この出会いがなかったら訴訟はおそらく提起できていないし、今もぶつくさ言いながら過ごしていたんだろうなと思います。
弁護団以外にも、応援や支援をしてくれる人、意見書を書いてくださった同業者の方、風俗のキャスト、ラブホテルの方、ストリップ劇場の方、色々な人が意見書を書いてくださいました。「人の手によってつながっている」という記録が、CALL4のサイトに残っているんです。自分1人の憤りは無力でも、こんなに広がっていったのはすごい力だなぁと思います。

裁判官によって答えは違う。だからこそ、裁判以外の場所でたたかうことも必要
松岡:
もちろん最初の一歩は、FU-KENさん自身の憤りと、その一歩がなくては始まらなかった。でも、その先に人のつながりが、いつの間にか歯車になって回っていくんですね。
判決の話に移っていきましょう。東京二次は地裁判決が出て、次は高裁判決を待つ、というところですが、まずは地裁判決どうでしたか?
鳩貝:
地裁判決は昨年8月にありました。原告8人みんな伝え切った!という気持ちで、だいぶ期待していたのですが、判決の内容自体は思ったようにはいかず、みんなで脱力した、という感じでした。
その日の午後に札幌高裁で、24条についても画期的な違憲判決が出たので、気持ちを持ち上げ直して、「裁判官によって差があるのかな」「やっぱり東京地裁厳しいらしいからそういうことかな、悔しい」という思いを噛み締めていました。
高裁の意見陳述をする前に、改めて判決文をじっくり読み込んでいくと、「同性カップルの婚姻に反対の人が少なからずいるから、社会的承認が得られたとは言えない」というくだりがありました。数字とか統計データとかで論理的に見せかけていますけど、同性カップルを区別しておきたいという差別ありきの結論に持って行かれたようにも感じて悔しい思いと怒りが沸々と大きくなっていきました。
だから高裁での意見陳述では、原告みんな怒りのボルテージがかなり上がって(笑)、地裁判決に物申したいっていう気持ちが半分以上を占めていたんじゃないかなというふうに思います。
松岡:
幸い高裁判決はどれも踏み込んでいて、同性カップルが婚姻制度を利用できないことが違憲だと言い切ってくれている判決がずっと続いているので、最後の高裁判決がどう判断するかというのはすごく注目しています…それがプレッシャーになっている面もあるとは思うんですけど。
鳩貝:
そうなんですよ〜(笑)。原告みんなで顔合わせると私たちがやっちゃったらどうしようみたいな話になります。
実際、唯一合憲的な判断を下された地裁の原告さんたちは「私たちの言葉が、あるいは私たちの経験が人の心に届かなかったんじゃないか」とおっしゃっていたりもします。「せっかく最高裁まで行ってるのに流れを止めてしまうんじゃないか」という気持ちもあります。
あと、LGBTQや同性婚に反対する動きが目立ってきていることもすごく不安です。
地裁の判決で、「婚姻制度というものは、元々同性愛者の存在が念頭になく作られた」っていう話があり、それは「同性愛者を結婚させない」という意図のものではないわけですよね。
でも、異性間でしか結婚できないっていう状態が何十年か続いていく中で気がつくとそれが『伝統』とかいうものになっていき、『異性婚こそが普通です』という価値観になっていくわけですよね。だとすると、同性婚に違和感を感じてる人がいるっていうだけで結婚させなくていいって結論を出すのはおかしくないですか。多数派の論理ってわけでもないのに。(異性婚のみを許す制度が温存されることによって)同性愛差別が再生産されていくことに、すごく「いじめられてる」という気分になってしまいます。…だからこそいい判決をもらわなきゃってかなり力んでますね。
FU-KEN:
最高裁で、接客従事者の尊厳を害する可能性のある仕事だから給付は認められないと裁判長から読み上げられた瞬間に、裁判をやったことを後悔するくらい最悪なことを言われてしまったなって思いました。ぼんやりと『社会通念が…』とかではなく、『働いている人の尊厳をあなたたちは害していますよね?』という、まるで鬼か悪魔のような所業であると最高裁に言われてしまった…。裁判をしなかったら公的には出てこなかった言葉なのかもしれないから、最悪だ…と思いました。そして、同業者から『なんてことをしてくれたんだ』とバッシングを受けるだろうし、世の中からも偏見の目でみられてしまう…と思っていたんですけれど、その時に弁護団の亀石先生が、「裁判長の反対意見がある」励ましてくださったんです。
こちらが伝えたかったことは全て裁判長には伝わっていたということ、そして多数意見だった他の裁判官たちには何も伝わっていなかった、ということが読んでいくうちにわかりました。
訴訟を始めるにあたって最初、私は、「最高裁までいければ、最高の知性を持つとても賢い人たちが『正しい』答えを出してくれるのだから、負けたら私この仕事やめようかな。」って思っていたんです。でも裁判を進めていくうちに、裁判官によって答えが違っているってことに気づいたんです。答えは一つじゃなかったんだって。
その理由について考えたときに、裁判官の経験や価値観がその違いを生んでいるのかなと、私はそう思ったんですね。つまり、それぞれの時代の社会通念によって答えは移り変わるし、裁判官の感覚や価値観も時代によって変わっていくということなんだと思います。だから、最高裁の判決を受けて『これで全然終わりじゃないなぁ…』と思いました。むしろ、この判決に対してまた戦っていきたい、戦って行かなきゃいけないし、ここで諦めたらもうどんどんそう(価値観が再生産されて)行っちゃうんだろうなって感じました。
松岡:
私も同じ印象を持っていたんですよ。最高裁が何か判断したらそれでルールが確定して、社会はそういうもので最高の知性を持つ人たちが決めるものなんだって。もちろん判例はそういう効果を持つものだと思いますが、判例も訴訟の積み重ねで変わっていく。一つの判例は単なるマイルストーンで、社会や世論が変わったり、政治状況が変わったりすると裁判も変わっていくのかなと思います。結婚の自由をすべての人に訴訟でも、一次の訴訟では地裁でバラバラの判決が出ていました。でも、高裁では揃いつつあるのが今の状況ですよね。

公共訴訟は「わたし」の困りごとを社会とつなぐ選択肢のひとつ
松岡:
一人一人の「わたし」の経験からスタートして、当事者の間で共通する課題や、次の世代への課題を通じて、『私だけの問題じゃないんだ』と自覚していくプロセスを感じてきたと思います。
そこで最後の質問として、「公共訴訟」ってなんなんだろうかということをお聞きしたいです。
まさに、お二人が感じてきたことと繋がると思うんですね。スタートは自分のためだったはずの訴訟が、実は社会のためでもあるようなものだったりする。それが公共訴訟なのかなって思いました。例えば、公共訴訟というたたかい方を選んだ理由とか、訴訟によって社会を変えていくことについて、お二人がどう思っているのかを聞いていきたいと思います。
鳩貝:
急に難しい話になりましたけど(笑)、東京二次は、集団訴訟で、しかも二番手(の訴訟)で、前を歩く原告たち、弁護団の姿をみながらやってきているという意味で(セックスワークにも給付金を訴訟とは)状況は少し違うかもしれないです。市民活動を経て、個人的なことは社会的なことである、社会が変わっていく必要があるんだというところに確信自体はあったので、私の場合は『個人の権利を主張する』っていうところからスタートしたわけではないのかなと思います。
社会課題の解決のために提訴をして、むしろその訴訟のプロセスの中で、個人の思いや経験が呼び起こされ、それをまとめあげていく過程で、言葉にすることを得てきた、という感じでした。多分全ての原告さんが、陳述書を書くのに泣きながら己と向き合ってきたと思うんですよね。パートナーとも、お互い陳述書を書くときは部屋にこもって、個人の作業として追い込んでやってきました。個人の課題をみんなに伝わるように、どうやって言葉にしていくかっていうプロセスが、訴訟だからこそできたのかなという気がしています。ただ訴訟だけじゃ終わらなさそうだ、国会が動いてくれないと法制化されない、という面はありますけどね。
FU-KEN:
差別って当たり前にダメなことだから正してくださいっていうだけのことなのに、政治に対して働きかけるためには数が必要で、『理解してもらわなきゃいけない』とか、頭を下げて署名してもらわなきゃいけないんですよね。なんでこっちが頑張らなきゃいけないんだって私は捻くれているから思ってしまう。でも、裁判は、1人で戦えるし、もっとわかりやすくて手っ取り早いです。
セックスワークの権利をめぐるたたかいは始まったばかりなので、これからまた政治に働きかけなければいけないとは思っています。ただ、裁判を通して声をあげること自体は、投票に行くくらいの、「生活」の中にある大事な行動なのかもしれないなと思いました。
CALL4さんや支援者の方々の存在がハードルを低くしてくれたっていう側面はあるんですけど、裁判を起こす権利を誰もが実は持っているということは、多くの人に知られてほしいと思います。
松岡:
私たち個人のそれぞれの生活の中でぶつかる制度の壁に対して、「訴訟」という選択肢があって、すごく大変なことだけど、1人から始めることもできるということですよね。今日はセックスワークに関することと、婚姻の平等に関することでしたけど、もっと違うテーマで、それぞれの生活の課題が実はあると思うんですね。みんなが、私だけじゃない経験として、国や社会を変えるために裁判できるかもしれないって思えると、公共訴訟ってもっと広がるんだろうと思います。
私自身もゲイの当事者として、自分の過去を振り返ると、たとえばゲイであることをカミングアウトした後にそのことを誰かに勝手に暴露されてしまう、いわゆる「アウティング」をされた時に、仕方ないことだって思っていたんですよね。だって自分が変でおかしいんだから。
珍しいことだから暴露されても仕方ないって思ってしまっていたんです。でも、裁判をきっかけに違うのかもしれないと思いました。一橋大学で起きた、アウティングされた方が亡くなってしまった事件から、性のあり方はプライバシー情報で、自分だけが管理できるものであって、勝手に暴露しちゃダメなんだと。
マイノリティとして生きていたことで、自分がおかしいし、変だし、社会を変えるなんて考えたこともないという時期が長くありました。でも、同じような経験をしている人と話したり、先人たちの活動、事件、訴訟とか、ニュースとかをみていると、自分のせいじゃないんじゃないのかな、と思うようになっていって、変えるために行動を起こせるようになるんじゃないかと思うんですよね。
私は情報発信を行っていますが、訴訟という選択が自分にもありえたのかもしれないな、全然他人事じゃないなって思うんですよね。
だから、自分の生活の中の違和感を、訴訟やCALL4を支援するという形で、何かしらサポートをして解決していくこともできるかもしれない。そういうことが個人の話から社会を変えていく一歩につながっていくのかなと思っています。

おわりに
もう一度、想像してみてください。
あなたが、もし大好きなパートナーと結婚できない立場に置かれたら。
あなたが、もし職業を理由に国から不当な扱いを受けたら。
思い浮かぶ言葉をメモして、最初の言葉と見比べてみてください。
ふたりの原告の物語は、あなたの想像と共感の裾野を広げたのではないでしょうか。
あるいは、あなた自身の経験とどこかで響き合うものがあったのではないでしょうか。
場所や時代が変われば、2人の原告の物語は、あなた自身の物語だったかもしれない。そんな気づきを心の片隅に留めておいていただければ、世界は少しだけ、残酷なものでなくなるのかもしれません。
鳩貝啓美さん(結婚の自由をすべての人に訴訟・原告 )
1965年千葉県生まれ。臨床心理士。30代からレズビアンサポートのボランティアを始め、2011年よりNPO法人レインボーコミュニティcoLLabo代表理事。2021年3月、法律上の性別が同じ同性カップルが結婚できないことは憲法違反だとして、「結婚の自由をすべての人に」訴訟(東京二次)を提訴。今年11月、控訴審判決が予定されている。
FU-KENさん(「セックスワークにも給付金を」訴訟・原告 )
デリバリーヘルス事業を関西で経営する女性。2020年9月、新型コロナウイルス対策の持続化給付金などの支給対象から性風俗事業者を除外した国の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、「セックスワークにも給付金を」訴訟を提訴。今年6月、最高裁第一小法廷は「合憲」と判断して上告は棄却された。
MC:松岡宗嗣さん(ライター/一般社団法人fair代表理事)
1994年愛知県生まれ。政策や法制度を中心とした性的マイノリティに関する情報を発信する一般社団法人fair代表理事。ジェンダー・セクシュアリティについての記事執筆や、教育機関・企業・自治体等での研修や講演を多数行う。著書に『あいつゲイだって—アウティングはなぜ問題なのか?』(柏書房)、『LGBTとハラスメント』(集英社新書) ほか。







