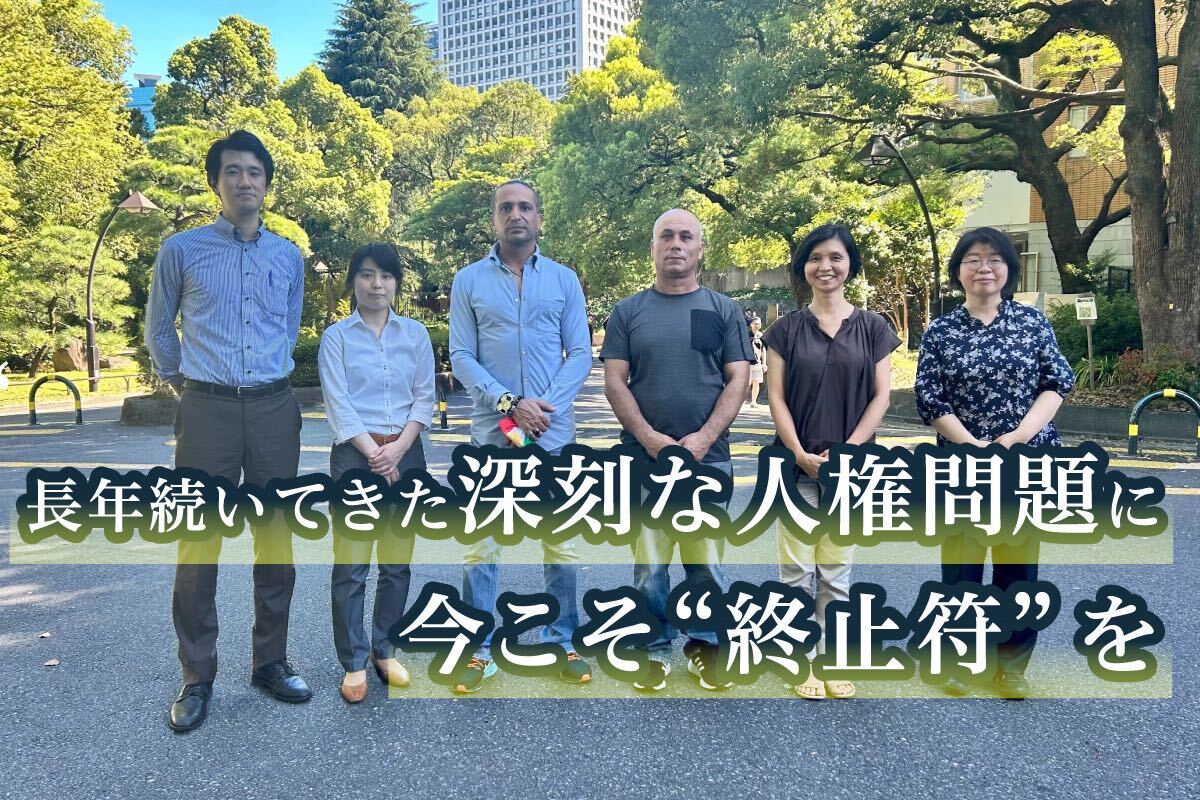「自分は動物じゃない」そこまで言わせる日本の入管収容は国際法違反である
 2022.7.5
2022.7.5
「自由権規約」違反を問う訴訟を支える、弁護士たちのストーリー
「人をひとつの場所に閉じ込め、いつ出られるか分からないとなったらどうなるか。その人の身体と心に取り返しのつかないダメージを与えます。出てきても治らないほどの」
2020年8月、日本の難民申請者ふたりに対して出入国在留管理庁(以下「入管」)が行った長期間の収容について、国連で「意見」が採択された。収容は「国際人権法に違反する」ため、「必要な措置を講じるように」、「補償を受けさせるように」、そして「出入国管理及び難民認定法を見直すように」という内容だった。
それでも収容の運用を改めず、補償を行わない国に対し、ふたりは収容の違法と、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)の国際法違反を問うて訴訟を起こした。
これはふたりの訴訟をサポートする弁護士たちのストーリーである。
イラン出身のサファリさんとの出会い(駒井知会弁護士のストーリー)

「小学校のころ西ドイツに住んでいて、現役のベルリンの壁を見ていた」と話すのは駒井知会弁護士。
「西側にたくさんの白い十字架があって、それは東から西に逃げてこようとして撃ち殺された政治難民の、遺体の入っていない墓だった。その光景が忘れられず、難民支援を志した」
イギリスで国際難民法を研究していた駒井弁護士だが、「日本国内の方が難民認定の状況が良くないと知って」帰国し、弁護士として難民支援を始めた。その中で、今から5、6年前、東日本入国管理センターで、被収容者でありながら、他の被収容者のためにペルシャ語の通訳をしていたイラン出身のサファリさんと出会った。
「祖国で激しい迫害を受けて逃げてきたサファリさんでしたが、明るいお人よしのお兄さんでした」
「それが、長期にわたる収容と短期の解放を何度も繰り返され、血を吐いて、面変わりしてしまった」
2019年、長崎県大村の入国管理センターでナイジェリア国籍の男性が餓死した頃、全国の入管収容施設でハンガーストライキが広まった。
「全国で100人以上の人がハンストをした。精神的に極限状態にまで追い詰められて、『自分たちにはこれしかできないから』と言って。サファリさんもです」
被収容者たちがハンストをしたのは、入管が「収容に耐え難い傷病者でない限り、無期限で収容を継続する」という運用を続けていたためだ。
結果、7月から入管も、ハンストで極度に衰弱した収容者たちに対して「仮放免」(一時的に収容を停止し身体拘束を解く措置)を出すようになったが、その運用は非人道的なものだった。
「入管は、ハンストで身体を壊した難民申請者たちを、仮放免で2週間だけ施設の外に出し、2週間経ったら無期限でまた再収容するという運用を繰り返すようになった。まるで見せしめ。人の命をもてあそぶとしか言えないやり方でした」
サファリさんも身体を壊して、2019年7月31日に仮放免された。その後2週間の間、駒井弁護士たちはサファリさんを守ろうと、仮放免を継続するためのさまざまな申立てを行った。
「しかし2019年8月14日、仮放免から2週間が経過したその日、サファリさんは目の前で連れていかれた。ガタガタ震えて、『でも絶対逃げない、難民として守ってほしいとお願いしている立場だから』と言いながら。そのときのことは一生忘れない」
「そこまで入管はやるのかと思った。こうした2週間の仮放免と収容の繰り返しは3度にわたり、サファリさんはうつ病に罹患しました。強制的にうつ病を発症させ、この人をこんなつらい状態にした『運用』に、誰も責任を取らないなんて、どう考えてもおかしいと思った」
トルコ出身クルド人のデニズさんの苦しみ(髙田俊亮弁護士のストーリー)

「8月14日、品川の東京入管でサファリさんが連れていかれるのを目の当たりにして、私の戦いも始まりました」
「入管の1階の待合室で、駒井弁護士、鈴木弁護士に会って、『戦う覚悟はできています』と告げました」
「学生のころから国際人権法に関心があり、国際人権NGOでも活動した」という髙田俊亮弁護士は、弁護士1年目から難民申請の件に関わっていた。本件では、トルコ出身クルド人のデニズさんへの法的支援を担当している。
「デニズさんも、祖国で迫害を受けて日本に来ました。しかし難民認定は認められないまま、何回も繰り返し収容されました。3年半にわたる長期間の収容もあったし、施設内で暴力も振るわれた」
髙田弁護士がよく憶えているのは収容中に会ったときのことだという。
「見た目もげっそりしていて、『入管の中の白い壁を見ると苦しくなる』と話すんです」
「日常で暮らしていると白い壁はよくある。でもそこにしかいられない、いつ出られるかも分からないとなると、日常が非日常に変わってしまうという恐ろしさがある。長期間、無期限の収容は、こうやって心身を蝕(むしば)む」
「こうした収容は合理性も必要性も、拘束目的に対するバランス(比例性)も欠く。『恣意的拘禁(しいてきこうきん)』です。国際法に違反する人権侵害であることは明らかです」
2カ月後の2019年10月、髙田弁護士ら弁護士のチームは、「サファリさんとデニズさんに対する収容は、自由権規約9条に違反する」として、国連の「恣意的拘禁に関する作業部会」に通報した。
第9条1項
すべての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する。何人も、恣意的に逮捕され又は抑留されない。何人も、法律で定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われない。
ここでうたわれているのは、「人はすべて、自由であることが原則。例外的な身体拘束のためには厳しい条件を付すべき」ということである。
自由権規約は人権保障を規定する多国間条約で、1976年に発効し、日本は1979年に批准している。恣意的拘禁作業部会は、国連人権理事会の決議に基づいて設置された専門家グループで、「恣意的な拘禁」が疑われる身体拘束を調査する。
通報を受けて、作業部会はふたりの収容につき調査を始めた。
そもそもの問題は「全件収容主義」(鈴木雅子弁護士のストーリー)

「私は弁護士になる前に、もともとは法律事務所の事務局として、難民申請者と友達のような立場で関わっていました」と語るのは鈴木雅子弁護士。
1990年代は、クーデター後に逃れてきたミャンマー難民が多かったという。
「弁護士になった後も、難民や入管、外国籍者の問題にずっと関わってきた。その中で、難民認定率が1%を切り、収容が長期化するなど、外国籍者を取り巻く状況がどんどん悪くなってきているのを目の当たりにしてきた」
2019年は、大村の収容施設での餓死、ハンスト、繰り返す収容と、「外国籍者の状況が極限状態まで来た」年だったと鈴木弁護士は言う。
「仮放免や収容の運用は、入管の裁量が広すぎる」
「日本の入管のそもそもの問題は、退去強制令書さえあれば入管の一存で外国籍者を収容できてしまうという『全件収容主義』、これを許容する入管法にあります」
退去強制令書だけで収容できるということはつまり、収容に際して裁判所でチェックする機会が与えられないことと表裏一体であると鈴木弁護士。
「これも自由権規約に違反しています」
第9条4項
逮捕又は抑留によって自由を奪われた者は、裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができるように、裁判所において手続をとる権利を有する。
この条項では、「人の身体の自由を奪う場合は、行政の片面的判断ではなく、司法によるチェックが必要」という原則がうたわれている。
イギリスの収容施設で知った処遇の違い(浦城知子弁護士のストーリー)

「裁判所に収容をチェックする機会がないということは、収容する機関(入管)が自らその正当性を判断するということ。これでは中立性がまったく担保されません」、そう話すのは浦城知子弁護士。
「人権保障にはどう考えてもつながらない」
「弁護士になって難民問題や入管問題を受ける中で、2014年、イギリスの入管収容施設に視察に行った。そのとき見たものは、処遇も、手続も、日本と全くスタンスが違うものでした」
「日本が『全件収容主義』で原則収容できてしまうのに対して、イギリスにおいて収容は例外的な処遇です。逃亡の恐れがない限り、保釈(※)を認める。例外的に施設に収容する間も自由に過ごせる。中で働くこともできるし、図書室で本を読むことも、インターネットで調べものをすることもできる」
それだけではない。日本では仮放免を申請すると2~3カ月待たされ、不許可却下の場合に理由も知らされないが、イギリスでは、裁判所に保釈を請求すると、基本的に3日以内に結論が出て、理由が明らかになるという。
「本来はこうあるべきだと、強く感じました」――日本に帰国した浦城弁護士は、訴訟を通じて収容問題と戦い始めた。
「訴訟をする中で1件だけ、仮放免を勝ち取ることができました。しかしそれでも2年以上の長い時間がかかった。これでは勝てても当事者に対する救済手段として不十分だと思った」
「国連への通報は6カ月で結論が出る。これは早い、有効な手続きだと思いました」
通報に応じて、2020年9月、国連の作業部会は、「サファリさんとデニズさんに対する入管の収容は『恣意的拘禁』に当たり、自由権規約9条などに違反する」という意見を出した。意見は、日本政府に対し、「国際的規範に適合させるために必要な措置を講じるよう要請する」「ふたりに補償の権利を与えるのが適切な救済措置である」「出入国管理及び難民認定法を見直すよう要請する」と続けた。
しかし政府はその後も動くことがなかった。
「今まで、自由権規約、国際人権条約は日本の裁判所で十分に反映されてきてこなかったという実情はありました」と浦城弁護士。
「でもそれは、今まで積極的に主張してこなかった弁護士の責任でもある。このケースでは国連の意見も出ているし、きちんと主張していこうと思って、国際法を根拠に提訴することにしました」
※イギリスでは保釈(Bail)と呼ばれている。
国際法は単なる理念ではなく、法規範(小川隆太郎弁護士のストーリー)

2022年1月、サファリさん・デニズさんは5人の弁護士とともに、国を相手に訴訟を提起した。
無期限の収容、必要性・合理性などを要件としない収容、裁判所がチェックする機会も与えられない収容。これらは国際法(自由権規約)で禁止されている「恣意的拘禁」にあたって違法であること。その根拠となっている入管法も国際法違反で無効であること。収容によってふたりに生じた損害を国は賠償すること。――自由権規約には、「違法に逮捕され又は抑留された者は、賠償を受ける権利を有する」(9条5項)とある。
「私たちは、この訴訟を通じて、『国際人権法は単なる理念ではなく、法規範だ』ということも伝えていきたいと思っているのです」というのは小川隆太郎弁護士。
「国際人権法が法規範であると明言されれば、同じように入管や刑事施設、精神病棟で恣意的拘禁に苦しむ人たちもが国際人権法に守られるようになる」
「私がこの分野の仕事を始めたのは、学生のときに9.11が起こって、イラク問題を入り口に海外の人権状況に関心を持ったのが始まりです」、小川弁護士は振り返る。
「それで大学生の時にボランティアしていた国際人権NGOヒューマンライツ・ナウで『アフリカンナイト』というイベントをやったときに、日本にいる難民申請中のアフリカ出身者に、『海外の人権問題に取り組むのも大事だが、その結果、日本に逃げてきて日本でも困っている私たちのような人がいる』と言われた」
「ハッとしました。海外と日本国内の両方の人権問題に取り組もうと思った。それで弁護士になった当初から難民事件は受けていました」
「事件を受ける中で、病気にならないと仮放免してもらえない入管収容の実態を目の当たりにして、在留資格が『人権を享有する前提』のように考えられていることが問題だとずっと思っていた。人権は、すべての人に保障されるものであって、在留資格の範囲内で国から裁量的に与えられるようなものではない」
在留資格は人権保障の前提ではない

駒井弁護士がうなずいた。「在留資格が認められないことによって、人間が人間でなくなるわけではない」
5人は国連の作業部会への通報に際してチームを組み、訴訟に向けてサファリさんとデニズさんをサポートしながら、議論を重ねてきた。5人の議論は、単にふたりの事件にとどまらず、収容の問題、外国籍の人びとの暮らし、ひいては日本社会全体のあり方に関わるものだった。
「いま、収容は、被収容者に『耐えられない、帰ります』と言わせるための武器として使われている」
「これまで、『祖国で迫害を受けて死ぬかもしれなくても、人間として死にたい』と言って、帰国を決意する収容中の難民申請者の方々を何人も見てきた。彼らは口々に、『自分は動物じゃない』と言った。収容が彼らに『自分たちは人間として扱われていない』と感じさせているということです」
「そこまで言わせるカラクリが日本に残っていることは、日本社会に対する脅威です」
入管だけではない、横断的な問題でもある

「恣意的な拘禁が道具として使われているのは、入管の事件に限りません」、駒井弁護士の話を受けて指摘するのは鈴木弁護士。
「刑事事件では自白を強要するために勾留することが『人質司法』と言われている。精神医療の分野でも、本人の意思に関わらず強制入院させられる制度がある」
「多数派の『安心安全』のために少数派の人権を踏みにじることをいとわないことが、さまざまな分野でよく表れている」
「そもそも社会全体にとって何がいいことかも分からないのに」と、髙田弁護士も声を合わせる。
「多数派の『全体がよければ少数者は排除していい』という感覚が制度に反映されてしまっている」
「私たちがさまざまな分野で、社会的弱者になったときに、国家機関が徹底的に人間の尊厳をはぎ取っていく、それを社会として許していて良いのか」駒井弁護士が疑問を提起する。
身体の自由は根本的な人権

「社会的に弱い立場にある人たち、声を上げにくい人たち、マイノリティの人たちが特に身体の自由を奪われやすい」と言うのは浦城弁護士だ。
「彼ら彼女らの身体の自由が奪われることに対する抵抗感が、この社会には弱すぎる」
「人間が同じ人間でありながら他人の身体の自由を奪うことは、究極の差別だと思うんです」浦城弁護士は続ける。
「人を閉じ込めることは、同じ人間だと扱われていないという気持ちを抱かせること。被収容者が『私たちは人間だ、動物じゃない』という気持ちになるのはそこだと思います」
「身体の自由がどれほど人間にとって根源的な自由であるか」と小川弁護士。
「もし『いつまでか分からないが、ずっと一つの部屋、建物内にいて』と言われたら、誰でも発狂しそうになると思います。Covid-19が流行して『ステイホーム』と言われて、移動できないことがいかにストレスを伴う非人間的なことであるか、自由に動けることがいかに大事かはみんなよく分かったと思う」
「人をひとつの場所に無期限で閉じ込めるとどうなるか。精神的な影響などが出て、外に出てきた後も普通の生活ができなくなるんです」
サファリさんの診断書には、度重なる収容を経て、抑うつ状態からうつ状態へ移行していったことが記されている。
5人が裁判を通じて求める未来

「サファリさんとデニズさんのほかにも、苦しんでいる人はたくさんいる。理不尽な目に遭った人たちは、仮放免を受けても、Covid-19が落ち着いた後の再収容に怯えている。今もまだ収容されている人たちがいる」
「制度がおかしいということを分かってもらって、より多くの人の救済を目指したい」と髙田弁護士。
「『この裁判によって救われる人たちがいる』ということが、今も苦しんでいるふたりにとっても心にともる灯りになるといい」と駒井弁護士が続ける。
「日本の景気が悪くなり、内向きになって排外的になる中で、外国籍の人たち、非正規移民の人たちの人権保障の状況は悪化してきた。私たちもそれをずっと止めてこられなかった」
「この裁判が転換点になって、身体の自由という基本的な人権の保障が、裁量の範囲とかじゃなくて、きちんとなされるようになってほしい」と鈴木弁護士。
「特別なことをしているつもりはない」というのは浦城弁護士。
「日本の裁判所での前例はないが、自由権規約は存在し、解釈も確立している。あるべき判断がなされておかしくない。過去のハンセン病患者に対する扱いが間違っていたと明らかになったように、今までの入管法は問題があったということが、訴訟によって明らかになると思っています」
「その意味では、時代を少し先取りするだけの訴訟です」と小川弁護士が笑顔を見せる。
希望はあると5人は口をそろえる。5月31日に行われた東京地裁の口頭弁論期日では、大法廷の傍聴席が満席になった。市民が興味を持つことが、社会の人権意識の向上につながる。それは、日本がいずれ人権分野をリードする国になるための、第一歩でもある。

取材・文/原口侑子(Yuko Haraguchi)
撮影/神宮巨樹(Ooki Jingu)
編集/丸山央里絵(Orie Maruyama)