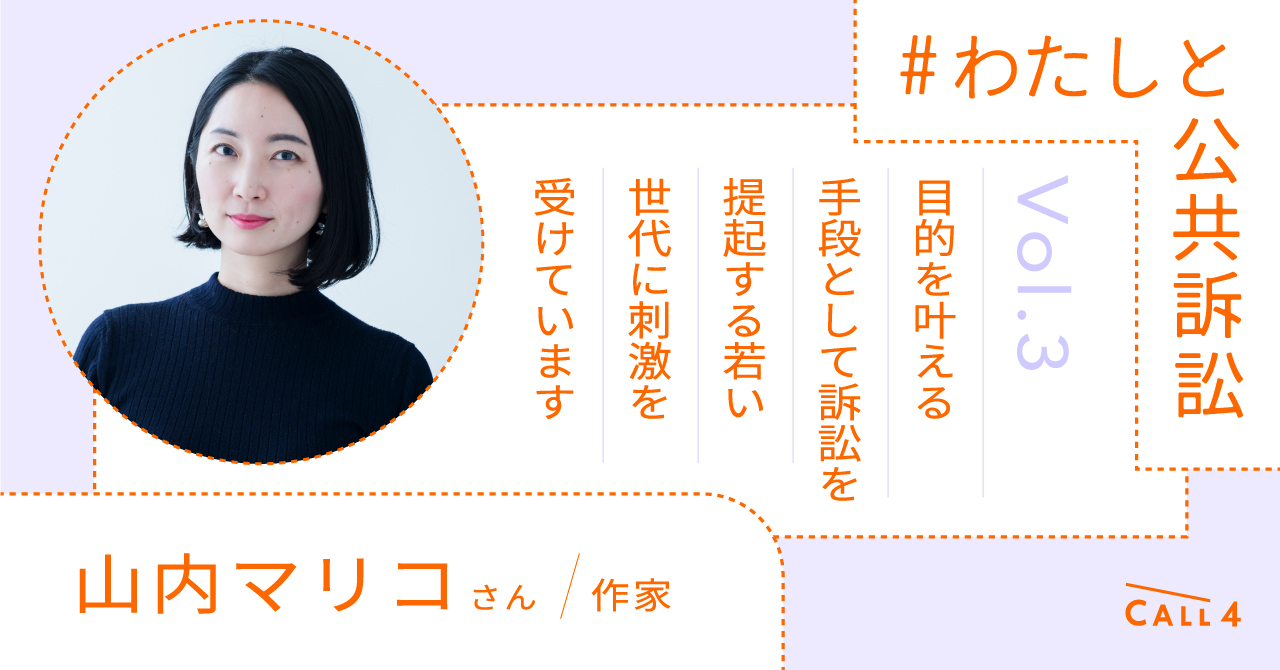小説家、裁判傍聴へゆく!|山内マリコ

リプロのことをあれこれ調べて書いただけで精根尽き果てて、なんと一年が経ってしまった。
前回、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」のことをできるだけわかりやすく、誰が読んでもスッと理解できるようにと、調べ物をしては噛み砕いて、書いて直しをくり返し、専門家の方にもチェックしていただいて、という工程を経て記事をUPしたところで、早くも燃え尽きてしまったのだ……。「それでは、〈「わたしの体は母体じゃない」訴訟〉とはどういうものだろう?」と振っておきながら! というわけで、前回までと文章のトーンが全然違うことをお許しいただきたい。
なぜこんなにも書きあぐねてしまったのか。それは取りも直さず、原告のみなさんの思いをできるだけ齟齬なく正確に伝えることの難しさに直面してしまったからだった。日本のリプロの現状、レベルの低さ、意識の低さを思うと、彼女たちの訴えをストレートに理解してキャッチできる人は、どれだけいるのだろうと思ってしまう。もちろん、だからこそ彼女たちは訴えを起こしているわけだが。
かく言うわたしも、原告たちの訴えが「自分の体から生殖能力を取り除くことを望む」ものだと最初に聞いたときは、頭の中に「?」が浮かんだ。それって一体、どゆこと?
わからないなら本人に訊いてみるしかない。
***
2024年6月の第一回期日。わたしは東京地方裁判所の前にいた。裁判にまつわることすべてがはじめてなので、まず「第一回期日」がよくわからない。「期日」というと最近は「期日前投票」で聞く言葉だが、期限の日、決められた日、前もって定めた約束の日、などなどに当たる。ただ裁判における「期日」は、関係者が裁判をするために定めた日を指す。「口頭弁論期日」「調停期日」などがあり、そういった予定をまるっと「期日」と呼ぶようだ。裁判に縁がなく中年になったので、そんな一般常識のようなことも、いちいちわからない。
「第一回期日では入廷行動を行うので、少し早めに来てください」とメールにはあった。入廷行動? 聞けば、よくニュースなどで見るあの、横断幕などを持って原告たちがずらりと歩いて裁判所に入っていく行為のことだという。あれに名前があったとは知らなかった。裁判所の敷地の中にカメラが入ることは許されていないため、マスコミ向けのプレゼンテーションとして行っているらしい。個人的なトラブル解決の裁判ではなく、社会的なテーマを扱う裁判の場合、そういった「見せ方」も配慮しなくてはいけないのだ。ちゃんと報道してもらって、たくさんの人にこの裁判を知ってもらって、関心を持ってもらうことが、とても大事。
というわけで、わたしたちは「第一回口頭弁論期日」の開廷時間よりも少しだけ早く、東京地方裁判所の前に集まった。
地下鉄霞ヶ関駅A1出口の階段をのぼると、目の前に現れるのが東京地方裁判所である。「裁判所」とだけ書かれた素っ気ない看板は、落書き防止のためか、透明の板でガードされていた。門扉は学校みたいなスライド式。その前の歩道に、この裁判の当事者、関係者、支援者や、マスコミの人たちがわらわらと集まってくる。ほどなく原告のみなさんが揃い、そのうちの一人、佐藤玲奈さんにお話を聞くことができた。短い時間の立ち話だったけれど、玲奈さんがこの裁判に原告として加わった経緯を教えてもらった。
玲奈さんはアロマンティック(他者に恋愛感情を抱かない)そしてアセクシュアル(性的欲求を持たない)を自認している。性行為によって子どもを持つことも望んでおらず、それどころか妊娠するかもしれない可能性そのものに違和感があるという。自分の性的志向をはっきり知ることができたのは、「ネットのおかげです」と言い切っていたのが印象的だった。
たしかにそうなのだ。ネット、とくにソーシャルメディアが一般化したのは、日本では2011年の東日本大震災以降のこと。使いこなせている人にとっては、それ以前と以後とで、世界はまるで違うものになった。自分の言葉を発信して、自分と同じことを考えていたり、感じていたりする人を見つけて、つながることができる。
性的マイノリティの人は、社会の常識が自分には当てはまらず、自分のことがよくわからなくて、深く悩むことが多いと聞く。そこへいくと玲奈さんは、ネットによって自分の性的指向にズバッとアクセスできて、自分一人だけではなくそういう人は他にもいるのだと知れた。これはすごく大きなことだ。
さらにそこから一歩進んで、「妊娠するために準備をさせられている」ことのへ違和感についてもネットで調べて、不妊手術のことを知ったという。
***
「不妊手術」と検索窓に打ち込むと、即座にAIが〈不妊手術は、生殖機能を永久に遮断する手術で、男性では「精管切除術(パイプカット)」、女性では「卵管結紮術」などが該当します〉と教えてくれる。
生殖能力を喪失させる目的で行われる手術といえば、誰もがパイプカットを思い浮かべるだろう。精子が精液に混ざらないように精管を切ったり糸で縛ったりする手術のこと。パイプカットしたと公表している芸能人も過去にちらほらいた。もっとも有名なのは大橋巨泉だろうか。彼が1972年にテレビの深夜番組でパイプカット宣言したことで、パイプカット手術というものが一般の人々にも知れ渡ったという。大橋巨泉は昭和のインターネットである。
男がパイプカットをする。その理由は様々だろうが、「もう子どもは欲しくないから」、もしくは「できると困るから」であることは確かだ。だって、それ以外でする理由のない手術だから。なんとなく、遊んでる男の人がやってるイメージ。深刻な手術というより、ちょっと軽い印象がある手術であることは否めない。
けれどこれが、女性が同じように「もう子どもは欲しくないから」「できると困るから」と思って、不妊手術を受けたいなと思っても、日本では受けられない。なぜか? 法律で禁止されているのだ。母体保護法という。
国家というものは「産む体」を持つ女性に、あれをしてはいけないこれをしてはいけないと、自分たちの都合に合わせて様々な制約を作る。戦時中は「産めよ増やせよ」一色だったが、戦後のベビーブームでは逆に子どもが増えすぎて困り果て、数を減らしたがった。それに合わせて法律はころころ変わる。
国民優生法(1940年〜1948年)、優生保護法(1948年〜1996年)と、法改正のたびに名前を変えて微調整され、いまは「母体保護法」という。この法律の目的は「母性の生命健康を保護」することにあるが、保護といっても駆け込み寺のようなものではない。人工妊娠中絶の手術を受けるには「本人及び配偶者の同意」が必要と定める法律である。
中絶したくても相手に逃げられて同意が得られず詰んだというエピソードを聞くけれど、それがこれ。この法律には一応、やむを得ない理由があれば「本人の同意だけで足りる」という条項もあるという。けれど実際には、同意書がないと手術できないと病院から拒否されたり、おろおろしているうちに中絶できる時期を過ぎてしまったり、といったケースも多い。その先に、赤ちゃんの遺棄に至るケースもある。
法律に書いてあることと、実際の運用は異なるという現実。
それでいうと、実は母体保護法は、男性にも適用される。だからパイプカットも法律上はNG、違法にあたるのだとか。だが実態は異なり、なしくずし的にOKということになっているらしい。同じ法律でも、男性に対しては目を瞑って、都合のいい運用がされているということらしく、いい加減なもんだなと呆れてしまう。女性のピルや経口中絶薬の解禁には何十年という時間をかけるのに、バイアグラの認可は秒で下りた話は象徴的だが、「不妊手術」に関しても同様の差別があるのだ。
男性は自由にやってもいいけど、女性はダメ。そんな性差別が、法律でもまかり通っていると思うと、イヤァ〜な気持ちになる。イヤァ〜な気持ちどころではないな。これは正面から怒っていいやつだ。だって憲法では、性別による差別は禁止されているのだから。朝ドラ『虎に翼』で何度も繰り返されたが、この国で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」のだから。
***
話を玲奈さんに戻すと、彼女は「不妊手術」を望むほど、自身の「妊娠するかもしれない体」に違和感を抱いているという。ネットによって「不妊手術」という、自分の違和感を解消する手立てを知ったが、日本国内では受けられないことがわかった。
ちなみに、避妊の手段として不妊手術を行うことは、海外ではわりと普通のようだ。韓国、中国、オーストラリア、米国、カナダ、イギリス、フランス、ドイツといった国では、コンドームやピル、ミレーナといった避妊手段の一つに、不妊手術という選択肢があることが知られている。それが日本では、法律で禁止されている。
玲奈さんはある日、リプロについて発信をしているSNSのアカウントで、とあるアンケートを行っているのを見つける。まさしく自分と同じように、「妊娠する体」そのものへの違和感についてのアンケートだった。

Vol.4につづく
次回期日は、10月29日(水)11時30分から、東京地裁・第708号法廷にて。
この日が判決最後の期日になる可能性があります。原告全員と代理人による意見陳述(法廷スピーチ)も予定されている見応えある期日。期日情報をチェックして、ぜひ傍聴に足を運んでみてください♪