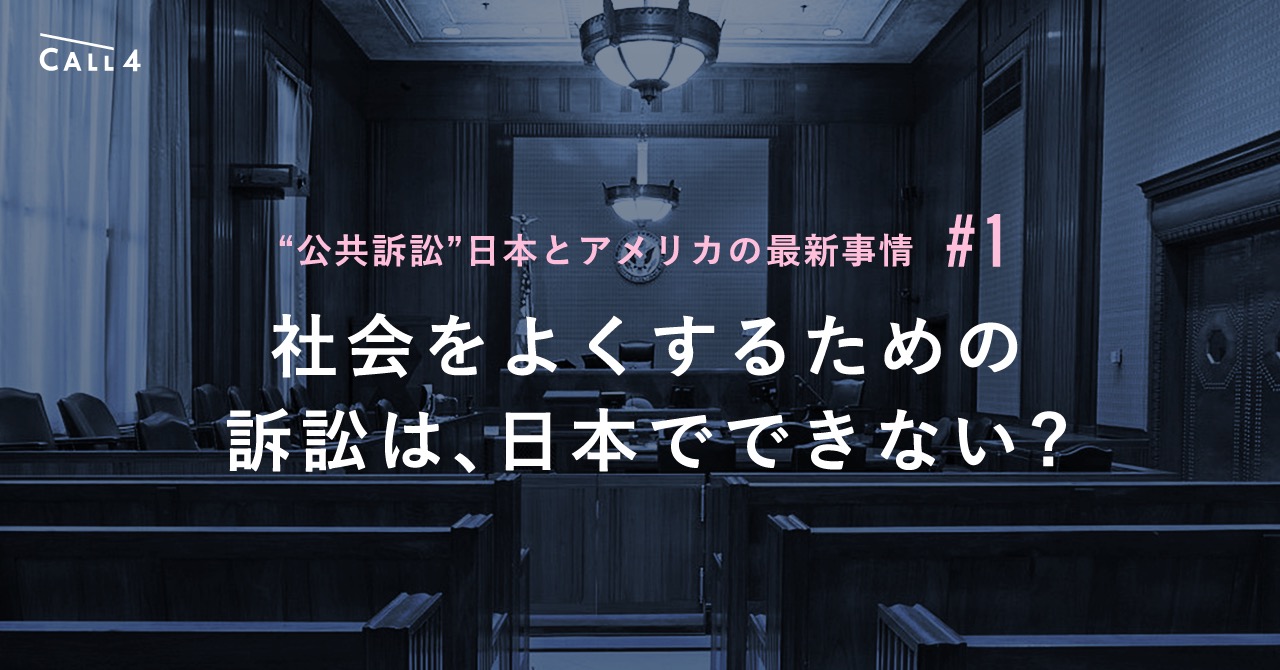やっぱりあきらめないことにした話
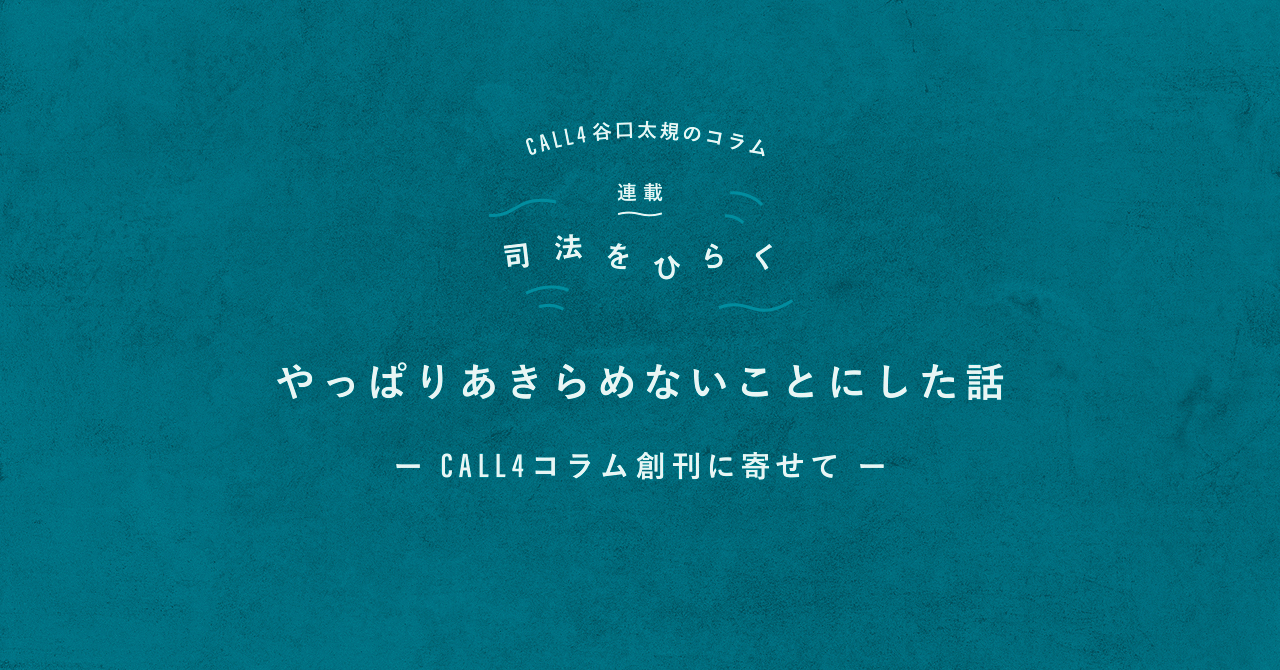
目次
スラジュさんの死
忘れられない事件がある。
ガーナ出身の男性スラジュさんは、日本人の妻と日本で暮らしていたが、在留資格を認められず、強制送還を受けることになった。ある日突然入国管理局は、彼を収容施設から連れ出し、飛行機に乗せようとした。手錠・足錠をつけ、声を出させなようにタオルで猿ぐつわをし、6人がかりで抱え上げ、運んだ。スラジュさんは「痛い、痛い」と思わず叫んだ。でも、身悶えするだけで、抵抗することはなかった。しかし、座席まで運び込んだ入管職員は、そこでスラジュさんを力の限り押さえつけ、前かがみにさせ、横から首を倒した。スラジュさんはそこで意識を失い、二度と目を開けることはなかった。
スラジュさんの妻と母が原告になって、その死の責任の所在を明らかにすべく国家賠償訴訟を提起した。私のほか数名の弁護士が弁護団を組み、代理人を務めることになった。費用をまかなうことは難しかったが、それでも放置しておくことはできない事件だと考えた。
国は、スラジュさんの死は、スラジュさんの心臓にあった極めて特殊な腫瘍による突然死だと主張した。
そんなバカな、である。手足を拘束し、何人もの男性職員が力の限り制圧しただけでなく、首を強く押さえつける中で息絶えているというのに、まさにその瞬間に、それまで問題なかった心臓の奇病が現実化して亡くなった、という主張である。そんな常識に反する奇想天外のストーリーを一体誰が信じるだろうか、私たちは国が提出した書面を見てそう思った。
圧倒的な差
ところが、国は次々とその主張を支持する医師を連れてきて、証言させた。これは心臓の奇病による死です、彼らはそう言った。国を相手にする訴訟-死因特定を専門にする法医学者は普段は国の機関の依頼を受けて仕事をしている-である上に、私たちにはほとんど払える費用もなく、国内で私たちに協力してくれる医師が見つからなかった。
それでも必死に英語の文献を読み、イギリスで、今回行われたのと同様の制圧行為が人の死をもたらすことを研究している専門家を見つけ出した。また、似たような体勢での多くの死亡事例が発生しており、アメリカの警察などでは注意が呼びかけられていることも突き止めた。3年にわたる審理、10人に及ぶ証人尋問を経て、一審は国の責任を認める判決を出した。苦労はしたが、正義はかなえられた、かに見えた。
しかし、控訴審になって、国はさらに多くの医師を連れてきた。まるで、日本のほとんどの法医学者が国に協力しているかのようであった。国は多くの予算をかけて研究者を雇い、再現実験までをやり、実験室の結果を持って問題ない制圧であったと主張した。一審で出せるだけの全てを出していた私たちはそれ以上の主張をすることが難しかった。
控訴審は制圧行為をした入管職員に直接話を聞くことなく、一審判決を覆した。基本法律論のみを扱う最高裁で事実認定を争うのはほぼ不可能に近い。飛行機の座席で崩れ落ちたスラジュさんは、心臓の奇病による死と片付けられ、入管が責任を問われることはなかった。
2010年にスラジュさんが亡くなってから、控訴審判決まで約6年。膨大な時間をかけた。あらゆる法律論を考えた。数百枚の書面を書いた。大学の医学部図書館にこもり、慣れない医学文献を読み漁った。翻訳費用も十分に捻出できず、皆で辞書を引きながら徹夜で外国の論文も訳した。それでも勝てなかった。スラジュさんの妻は、裁判が進行するにつれ、憔悴し、言葉数が少なくなっていった。
責任が認められなかった入管の施設では、その後も多くの人が亡くなっている。私たちが勝訴していれば、そこで入管のあり方を変えられたかもしれない。その後も続いた人たちの死を一人でも防げたかもしれない。しかし、それは叶わなかった。入管での人権侵害のニュースに触れるたび、虚しさと、自責の念を感じた。
大統領令を止めたもの
日本の司法と向き合うことに疲弊し、絶望を感じた。法律から離れ、別のことを学びにアメリカに留学した。豊かな自然がすぐそばにある田舎町で、ゆとりのある時間を、新鮮な新しい分野の勉強に費やした。心が洗われるような気がした。留学中に我々の上告が退けられたとの報を受けたが、どこか遠い話を聞いているようだった。
しばらくして、アメリカで大統領選挙が行われた。トランプ大統領が生まれた選挙だ。移民排斥を基本的な主張とするトランプ大統領は、就任後間もなく、中東の国々の人々の入国を制限する大統領令を出した。アメリカでは大統領の権限は強い。私はニュースを見ながら、ああ、自由と移民の国と言われたアメリカも、こうして変わっていってしまうのだなと思った。
同じ日、人々が街頭インタビューで「司法の出番だ。」と話す場面がテレビに流れた。えっ、と思った。画面が切り替わっても、しばらく動けなかった。日本では司法や訴訟がそんなふうに語られる場面を見たことがなかった。
それから、少しして、今度は、駆けつけた弁護士たちが空港の床に座って、入国制限を受ける当事者たちから話を聞き取る姿がネットで流れてきた。この訴訟を支援しよう、司法なら私たちの社会を守れるはずだ、という声がSNSに溢れた。何万人という人から、次々と寄付が集まっていった。その額は瞬く間に億に達した。
翌日、私は、連邦裁判所の門から上気した顔の弁護士が出てきて人々に囲まれる場面を、ディスプレイ越しに固唾を飲んで見ていた。
「裁判所は、大統領令を止めることを命じました。私たちの、自由と平等の勝利です。」彼はそう述べた。周りを囲む人たちが、地を鳴らすような歓声を上げた。
司法をひらく挑戦
いてもたってもいられない気持ちがした。胸の高鳴りを抑えられなかった。アメリカの最高権力者の威信をかけた命令を、移民の権利を侵害するからと、司法が止めた。それだけじゃなかった。人々が司法を信じ、司法を人々が支えている。そしてそれが、社会を守り、あるいは社会を変える確かな力となっている。
日本で、私は絶望する前にやるべきことをやったのだろうか。本当にやり尽くしただろうか。一つの訴訟の中では懸命に頑張ってきた。しかし私はもっと広い社会と向き合ってきただろうか。ここで起きてることをきちんと知らせ、より広い仲間を募ってきただろうか。
私が疲弊したとき肩を支え、背中を押し、困った時に知識や勇気をくれる人たちが本当はいたのかもしれない。司法という自分の持ち場を離れる前にまだやり残したことがある。
大学院を卒業し、少しアメリカで働いた私は、そんな気持ちで日本に戻ることとした。そして、仲間と出会い、CALL4を始めた。
CALL4というプラットフォームは、司法を社会にひらく試みだ。公共訴訟と人々をつなぐ実践だ。訴訟という形で立ち上がった人たちの声は、とてもパーソナルなものでありながら、同時に「わたしたち」のものでもある。それはわたしたちの生きる社会の公正さへの問いであり、わたしたちの自由へのチャレンジであり、わたしたちの未来についての話だ。だからこそ、わたしたちは声を上げた人たちを独りにしておいてはいけない。
* * *
共感は社会を変える。わたしたちは、本気でそう信じています。ここに始まるCALL4 コラムを通じて、一人でも多くの人が、この壮大で、けれどとても身近で、現実的なソーシャルチェンジに参画してくれることを願っています。
公共訴訟のこと、CALL4のこと、興味を持ってくれたらまずこのサイトを見てみてください。どんな思考も、どんな実践も、耳を澄ますことから、知ることから、始まると思うから。