奴隷のような20年間の牧場暮らし。どうして、助け出してあげられなかったのか
 2025.2.18
2025.2.18
障害者虐待を隠ぺいした恵庭市の責任を問う、原告の佐藤さんと中島弁護士のストーリー
遅くとも朝5時には起床。朝食は毎日茶碗1杯の飯に、お湯と生卵をかけたもの。50頭以上いる牛の餌やり、牛舎の掃除、搾乳……決められた手順を行うと日が暮れる。1年間365日、牧場の日課をこなす。
冬の特に寒い日、気温は氷点下20℃まで下がる。あかぎれした手に、牛の乳が温かい。暮らすプレハブには水道もトイレも灯油もない。作業を終えると四畳半の部屋で布団にくるまり震える。濡れタオルで体を拭く。髪の毛が伸びてくると、親方に牛用の巨大なバリカンで切られる。「耳切られるかなと思って」怖い。
春がきて、夏がやってくる。力仕事で汗だくになる。樽に貯めた水を汲んで飲む。虫の死骸が浮かんでいる。秋になればどんぐりを拾って空腹をしのぐ。
以前働いていた牧場から持ち込んだラジコンカーは壊れてしまって、もう長いこと部屋に飾ったままだ。ここにきて何年経ったのか、「数えてないから分からない」。会うのは一緒に働くふたりと、母屋で暮らすじいちゃんとばあちゃんと親方だけ。
「ほかの人らは言わないけど、俺は出たいと思ってた。やっぱり自由がほしかった」
でも、口にすると怒られるから「あきらめた」

弁護団によれば、佐藤さんは2001年から2022年までの約20年間を、この北海道恵庭市のX牧場で過ごした。牧場主の夫婦とその息子は、知的障害のある佐藤さんら3人を休みなく無償で働かせたばかりか、住み込み期間中の障害者年金をすべて引き出していた。
外部から相談が持ち込まれ、恵庭市はどんなに遅くとも2017年頭には佐藤さんらの置かれた状況を認識していたことが分かっている。そこで、“現代の奴隷”と言っても過言ではない生活から救い出せた、はずだった。しかし、市は虐待案件として扱わず、さらに5年以上も彼らを放置した。一体なぜなのか。
初めての出会い
「最初に、恵庭市にある障害者支援センターさんから、弁護団長の船山に声がかかったんです」と、中島 哲(さとし)弁護士は話を切り出した。

「相談は、恵庭市内の牧場に住み込みをされていた障害者の方がいらして、生活環境も劣悪であったし、どうも預金通帳の口座を見ると本来残っているべき残高がないようだ、ご本人たちの相談にのってほしい、という内容でした」
のちに弁護団長となる船山暁子弁護士は、札幌で障害者の問題にともに取り組む仲間に声をかけた。手を挙げた中島弁護士は一緒に面会先に向かい、そこで初めてのちに原告となる佐藤さんらに出会う。2022年のことだ。
「最初にお会いしたときは、やはり表情も硬かったですし、自分たちの置かれた状況がまだうまく掴めていない様子でした。ただ、お金はやっぱり返してほしいし、正直酷い目に遭ったと思っているとは明確にお話されていました」
「そうして話を聞くうちに、これはおそらく年金は使われてしまっているんでしょう、と。牧場主側に対する責任追及はしたほうがいいということが分かりました」
「さらに、どうも数年前に一度、恵庭市役所に話がいっていたらしいことも分かって、それを放置していた市の責任もあるんじゃないか、というところに行き着きました」
相談を持ち込んできた障害者支援センターは、恵庭市から業務委託を受けた社会福祉法人が運営しており、市から、障害者や家族等への相談支援、障害者虐待防止センターの役割などを請け負っている。
そのため、この段階で支援センターには責任追及にまつわるやりとりからは外れてもらい、弁護団が当事者と直接話をし始める。そして、さらに弁護士の仲間を募って、7人からなる現在の「恵庭市障害者虐待隠ぺい事件」弁護団が結成された。

地元の名士だった牧場主
事件の起きたX牧場は、札幌市街から高速を使って車で1時間ほど、恵庭市役所からもそう遠くない場所にあった。一帯はいくつもの牧場が隣り合っているようで、辺りに人気(ひとけ)はなく、草地がただ静かに広がっていた。
すでに閉鎖され荒野となったX牧場の敷地を沿道から望むと、佐藤さんが“ばあちゃん”と呼んでいた牧場主の妻が今も暮らす母屋が建ち、その横に佐藤さんが生活していた黄土色の四角いプレハブ小屋もぽつんと見えた。
このX牧場は、2016年に経営破綻して閉鎖されるまでは、50年以上存続してきた、地元ではよく知られた牧場だったという。全盛期には今は亡き牧場主が酪農経営で農林水産大臣賞を受賞するなど外からの評価も高かった。そして、この牧場主X氏は1991年から2011年まで、20年の長きにわたって恵庭市議会議員を務め、うち2年間は市議長までを務めた人物だった。
恵庭市には、1973年に設立された、知的障害者に住み込みで食事と仕事を提供する牧場主やそこで働く障害者が交流を行うための職親団体があり、その「育恵(いくけい)会」の会長もまたX氏だった。育恵会はX氏の亡くなった翌年の2021年には解散しているが、弁護団が調べたところ、かつての総会案内の連絡先には恵庭市障がい福祉課の名前があり、事務局機能を担っていた様子が窺えたという。X氏と市は深くつながっていた。

残された記録
弁護団が恵庭市の責任を追及することを決めたのには理由がある。前出の、日頃から恵庭市障がい福祉課と連携している障害者支援センターがこまめに記録し、保管していた「受理事件処理簿」の存在だ。そこに衝撃的な記録が残っていた。
2016年7月、支援センターに障がい福祉課のA主査らが来所したところから事は始まる。その日の対応記録欄には、障害者3人が住み込みをしている市内の牧場が閉鎖するかも知れず、急ぎで住む場所を探してもらう可能性があるので、今日は情報だけ伝えにきた、と言われたことが書かれてある。「どういう方なのか(中略)といった情報も一切ない状況」とセンター職員の困惑した書き込みも添えられてある。内容から、障害者3人というのが佐藤さんらを指しているとわかる。
そして半年後、今度は障がい福祉課のB主査から電話が入る。記録によれば、障がい福祉課は佐藤さんらの新しい就労先を見つけるため障害者手帳の取得に動いていたようだ。ところが、牧場主X氏から佐藤さんらを障害等級の判定日に連れていけなくなったと直前に言われてしまい、「プレハブに住まわされているなど劣悪な環境で、さらに年金などの金銭的搾取も疑われるため、市としては早めに介入していきたいと考えている。そのため、1/31の判定日を予定通り進めていきたい」ので、車での送迎だけ支援センターに頼めないだろうか、との依頼だった。
支援センター側が今の情報だけでは受けかねると答えると、B主査からは「4月の次回判定日に行くことになった」と返事があった。本当に先延ばししてよいのかを懸念したセンター職員は、障がい福祉課をその日のうちに訪問、そこでB主査からさらに詳しい経緯の説明を受けたことが記録されている。
今回の支援対象者は3人。長い人で40年近くX牧場で働いていて、全員が障害者年金を受給している。障がい福祉課が支援を始めたきっかけは、半年ほど前、育恵会の副会長からB主査に声がかかったこと。副会長から、会長のX氏が経営する牧場が潰れたらしいこと、そして牧場に通う獣医から聞いた話があった。伝聞の内容は、牧場で働く障害者が、X氏から「どこにでも行っていい」と言われてしまったと困っている、さらにうち1人は足が凍傷になってもいるようだ、というものだった。
この育恵会の副会長の話は、第三者からの虐待通報と扱っておかしくない内容だ。実際、B主査はその後に「虐待も視野に入れ、障がい福祉課で裏取りをした」と発言している。しかし、そこに看過できない発言が記録簿に続く。
裏取りをした結果、「農場のうち酪農が破綻していたこと、X氏が元市議会議員(元議長)であったことが分かり、対応気を付けるように達しがあった」、「破たんのことまでは市長決裁を取っており、障がい福祉課だけでなく、市としてことを荒立てずに支援していくという方針が立てられた」というのだ。
さらには、B主査がセンター職員に対し、「これはあくまでも市としてオープンにしている話ではない」、「もし◯◯(センターの名称)が虐待案件として扱うのであれば、このケースには関わってもらわず市単独で扱っていく」と言ったと書かれてある。
これらの記録からは、市の上層部からの指示の下、障がい福祉課が秘密裏に対応に当たっていたことが読み取れる。
なお、のちに恵庭市の調査委員会の聞き取りに対してB主査(役職当時)は、一連の記録は支援センター側の目線だとしつつも、その内容を否定していない。

虐待はないことにされた
B主査との話し合いの翌月、2017年2月には、支援センターの職員が、障がい福祉課のA主査らに同行する形でX牧場を初めて訪問した際の記録も残っている。
そこには、訪問先の牧場主X氏から、佐藤さんらには牧場仕事の代わりに農作業をさせる予定なので、「今すぐどこかに行かないといけないということにはなっていない」との話があったことが書かれてある。障害者年金については、「本人たちの生活のために使っている」と聞き取っているが、通帳の確認まではできていない。けれども、センター職員は佐藤さんら3人に聞き取りをし、「給料はもらってない」との回答を得ている。また、一行はこの日、真冬の冷え切ったプレハブにも入室し、ときに佐藤さんらが腹を空かせて廃棄野菜や野草を食べていることも聞いている。虐待の可能性は拭えなかった。
しかし、支援センターの記録には、佐藤さんらの過酷な暮らしを決定づける、生々しいやりとりが続いていた。訪問の帰り道、支援センターの職員が「虐待の通報はできる」と話すと、A主査は、強い口調で「なんの根拠があってそのようなことが言えるのか」と通報を制止したというのだ。
そして、以降は市が訪問を継続するとして話は結論付けられ、支援センターはX牧場の案件に関与できなくなる。結果、センターに残る次の記録は、佐藤さんらが弁護団とつながるおよそ5年後の2022年まで一気に飛んでしまう。
2017年のX牧場訪問当時のセンターの記録には、佐藤さんに関して、「きれいなセーターとジーンズ姿。ニコニコとしており、今回1番お話しをされていた。パンフレットを渡す前後、手の震えが見られた」と職員が彼をつぶさに観察した様子までが描かれていた。おそらく当日は佐藤さんの持ち前の人懐っこさが発揮されたのだろう。実はこの日だけ母屋で入浴をし、新しい服を着せられてもいる。けれど、決して彼はこのとき生活に満足していたわけではなかった。後のインタビューで佐藤さんに、外から人が来た時にここを出たいとなぜ伝えなかったのかを聞くと、こう答えが返ってきた。
「そこにばあちゃんがおったから。それを言うと、帰ったあとに何言われるか分からない」
支援の手はすぐそこまで届いていた。どうして、助け出してあげられなかったのか。

恵庭市の責任
「やはり『障害者虐待防止法』違反だと思っています。使用者虐待であれば本来、恵庭市は北海道に通報しなければならないのを、虐待ではないという処理をして通報しなかった。その不作為の違法性と、さらに一歩踏み込んで意図的に障害者支援センターが調査しようとするのを妨害、隠ぺいをしようとした作為に関しての違法性をまず第一に争っています」
2023年8月、牧場側だけでなく、恵庭市の法的な責任を問う訴訟を弁護団は提起した。事務局長を務める中島弁護士は、分厚いファイルをめくりながら現況を説明してくれた。
『障害者虐待防止法』とは、虐待によって障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐための法律だ。この法律では、障害者虐待の予防や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護などが地方公共団体の責務として定められている。
主な虐待例には、十分な食事を与えないなどのネグレクト(放棄・放置)や、年金や賃金を渡さないなどの経済的虐待も含まれており、2017年の訪問時点で少なくとも虐待の可能性が拭えないことを市は認識していたのだから、市の判断は裁量権の逸脱濫用で違法だと弁護団は主張している。
一方の被告の恵庭市は、育恵会の副会長から市へあった連絡はただの伝聞情報の噂話に過ぎず、通報ではなかった、当時虐待の認識はなかったと反論している。また、障害者支援センターは日頃から市に対して非協力的なところがあり、記録についてもセンター職員の邪推があるとして内容を細かに否認しており、裁判は事実関係についての確定のために時間を要している。
「ひと言で言うと、罪深いなと思っています」
中島弁護士はそう言うと、窓越しに大通公園の向こうに建つ札幌地裁を悲しみとも怒りともつかない表情で見やった。そして恵庭市には当時の責任だけでなく、今の責任があると思っていると続けた。事件がおおやけになった後も市に虐待に向き合う姿勢がまったく見られないからだという。
2023年夏、提訴の可能性が見えた段階で、恵庭市は事件の内部調査委員会を立ち上げた。しかし、第三者は入れず、資料も非開示(のちに裁判を通じて調査報告書は開示された)。恵庭市長は、「裁判が始まるので今の時点で何も言えることはない」と記者に発言しており、裁判をする以外の収め方がなかったんです、と中島弁護士は言った。

行政の担うべき役割
「見てください、可愛いでしょう」
取材中、中島弁護士は愛らしい男の子が表紙の冊子を突然差し出した。そして、「幼い頃の息子です。数百人の応募者からモデルに選ばれたんですよ」とにっこり笑った。
その息子さんは4歳のとき、重度知的障害と自閉症の診断を受けている。私的な体験になりますが、と前置きして、中島さんは過去のあるエピソードを教えてくれた。
発語はほぼなく、家の中を散らかしながら、声にならない声を発して走り回る息子さんの面倒に疲れ果てていた頃、中島さんはあるテレビ番組を観た。そこでは同じ自閉症の当事者が、文字盤を使って言葉を語っていた。「周りから奇異に見えていることは自分でもわかっている、でも止めたいと思ってもどうしようもないんだ」というような内容だった。中島さんは激しい衝撃を受けた。
「お前が一番つらい思いをしているんだね」と話しかけると、息子さんは涙ぐみ、そのまま親子で泣いて抱き合ったのだという。障害のある当人は、たとえ表現できずとも、生きにくさに誰より苦しんでいると中島さんが確信した瞬間だった。
「その息子も今は中学生になって、身長は妻を、体重は私を超えました」と中島さんは微笑んだ。
「障害のあるなしにかかわらず子どもはかわいいです。ただ、おそらく成人になっても、うちの子は本当の意味での一人暮らしができる状況にはならないと思っています。普通に考えて親が子どもより長生きはできないので、どこかの段階で手を離す必要があります」
「そうなったときに、行政が信頼できなくては困るんです。福祉事業者さんもですが、そこを監督する行政がきちんとしてくれないと安心して手を離せない、死ぬに死ねません」
変わらず穏やかに語られる言葉が、重く響く。
「今回の事件を恵庭市という、一つの地方公共団体だけの問題で終わらせたくないと思っています。障害者虐待防止法をきちんと運用しなければ、行政が責任を負うことになるのだということを世に知らしめたいんです」
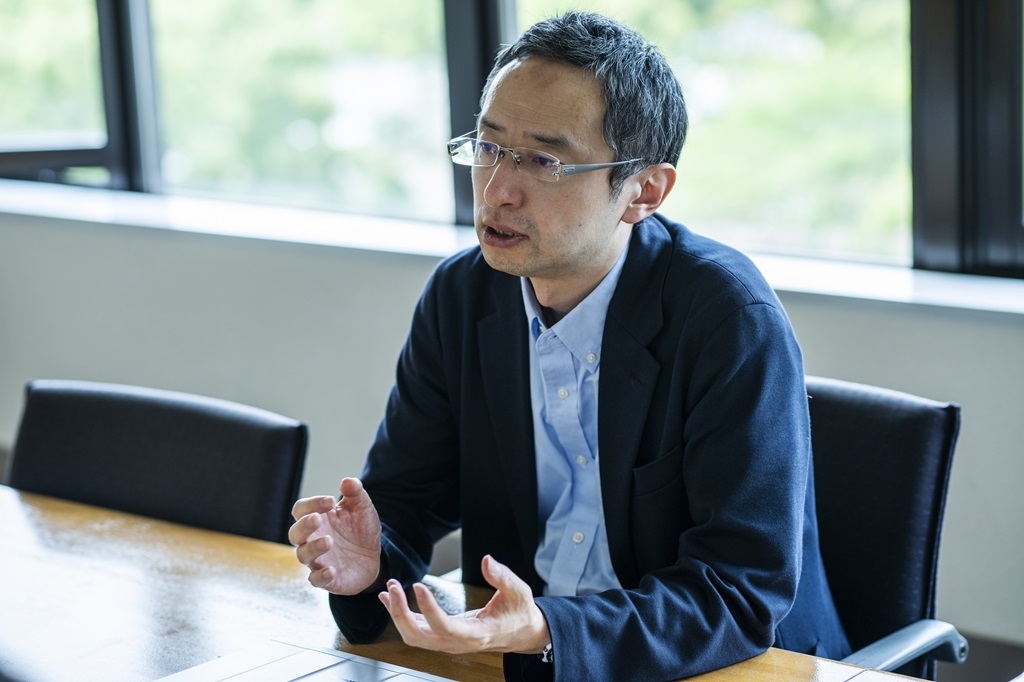
当たり前に支え合える社会へ
X牧場を出た佐藤さんは今、支援を受けながら、障害者向けグループホームの個室で一人暮らしをしている。障害者向けの就業支援の作業所に通い、週5日ほど、袋詰めなどの作業をして働いているという。
外の世界を知ったことで、今、被害を受けた3人には自分たちの受けた被害を人に知ってほしいという気持ちが芽生え始めているのだそうだ。佐藤さんに至っては、提訴してから1年ほどは傍聴席で一般傍聴人として裁判を見守っていたが、昨年11月から原告として顔を出していくことを決めた。
「やっぱり怒りだね」
佐藤さんは裁判を起こした気持ちを、そう言葉にした。そして、裁判を起こしたことで事実が明らかになっていき、多くの人が応援してくれていることについては、「うれしいです」とはにかんだ。
おかしいことにおかしいと声をあげ、周囲がそれに耳を傾け、支えていく。その営みが連なり、社会は少しずつ進んでいくのだろう。障害者もひとりの人間だという当たり前のことが、当たり前に認められる社会に向けて、この裁判には、原告と弁護団の譲れない矜持がある。それは2024年7月、最高裁に被害者の訴えが届き、障害者に対する強制不妊手術を規定した「旧優生保護法」に違憲判決が下されたことともつながる長い道のりだ。
取材の日、佐藤さんはお気に入りのラジコンカーを自ら持参していた。「これはスバルのインプレッサ」「エンジンを入れれば走るよ」などと屈託ない笑顔で一台ずつ説明をする彼はもう、ラジコンカーを外で自由に走らせることができる。お金が戻ったら「どこか遊びに行きてえな」と言う佐藤さんに、どこ行きましょうか、と問いかけると、「まずは札幌のまちをふらふら」と、楽しい答えが返ってきた。
彼にはもっと早くにそれができたはずだ、そう思うと言葉に詰まった。佐藤さんが自由を奪われていた時間は戻らない。せめて、彼が起こしたこの裁判が、障害者に自由な暮らしを保障するよう行政に楔(くさび)を刺すことを願った。

取材・文・構成/丸山央里絵(Orie Maruyama)
撮影/古瀬 桂(Kei Furuse)
