日本で家族そろって暮らす自由を、平等な制度を求めて
 2023.10.31
2023.10.31
日米同性カップルの在留資格をめぐるストーリー
まだ暑い夏の夜、康平さんとアンドリューさんの住むマンションを訪ねた。突然の訪問にびっくりしたふたりの愛犬リラが吠える。康平さんがリラをなだめている間に、アンドリューさんがアイスティーとアイスコーヒーを作ってくれた。氷の入った冷たいグラスを手にすると、汗がすっと引いていった。
冷房の効いた書斎のソファに座り、ふたりはこれまで20年弱の軌跡を語り始めた。説明するアンドリューさんの隣りで康平さんが静かに相づちを打つ。リラをなだめる手がやさしい。アンドリューさんはリラを康平さんに任せることに慣れていて、ふたりは冷房どう、「リラが興奮するから照明は暗めにしようか」と細かく確認し合う。
この穏やかな空気はどこから来るのだろうと、アイスティーを一口、息をつく。
差別の是正と家族生活を求める訴訟
康平さんとアンドリューさんはアメリカで結婚したふうふ。しかしふたりが同性国際カップルであることによって、アンドリューさんは康平さんの配偶者として日本に滞在することができない。
異性婚のカップルであれば、外国籍の配偶者も「配偶者」として日本での在留資格(※)を得られるにも関わらず、アンドリューさんには2019年の段階で30日から90日程度の「短期滞在」ビザしか付与されていなかった(なお、外国人同士の同性婚であれば一方が日本の在留資格を持つ場合はもう一方も「特定活動」の在留資格を得られるが、日米カップルのアンドリューさんにはこの資格すらも付与されなかった)。
2019年、アンドリューさんは、在留資格変更の不許可処分の見直しと「定住者」の資格を求め、訴訟を提起した。同時に康平さんとふたりで、日米の同性カップルに対する差別的取り扱いの是正と家族生活の自由を求めて国家賠償請求訴訟も起こした。
それに対して一審の東京地裁は、出入国在留管理庁(入管)がアンドリューさんに短期の滞在しか許容しなかったことは、外国人同士の同性カップルと比べても差別的取り扱いであるとして、日米カップルのアンドリューさんに対して「特定活動」資格すら認めなかったことについて憲法上の平等権違反を認めた。
「それは大きな一歩ですが、同性国際カップルが異性カップルと比べて著しく不安定な地位にあるという根本的な差別を解消したい」と、現在ふたりは二審目の控訴審を戦っている。
※在留資格:日本国籍を持たない人が日本に滞在するために必要な資格。「出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)」における法的な資格で、目的に合わせた在留資格を取得することによって、許可された期間まで日本に滞在することができる。
在留資格には、対象者や内容の異なる多種の資格があり、大きくは『居住資格』と『活動資格』の2つに分かれる。『居住資格』は、身分または地位に基づくもので就労制限はなく、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つが含まれる。もう一方の『活動資格』は就労制限があり、「短期滞在」や「留学」「家族滞在」など原則として就労できない資格、アンドリューさんの持っていた「経営・管理」など一定の職種にかぎって就労可能な資格、また法務大臣が個々の外国人に対して活動を指定して認める「特定活動」がある。

ふたりの軌跡と困難
康平さんとアンドリューさんは2004年、康平さんのアメリカ留学中に出会った。ほどなくして付き合い始めた彼らは、康平さんがアメリカの大学院を卒業した2008年までアメリカで一緒に暮らしていた。
「私はそのとき既に12年ほど働いていましたが、博士号を取るためにキャリア転換を考えていたところでした」
当時大学に勤務していたアンドリューさんは語る。
「ところが国内出張から帰ると、迎えてくれた康平が、アメリカでの就職事情が厳しいから大学院を修了したら日本に帰らないといけないかもと言い出しました」
折しもリーマンショックが起こったころだった。康平さんは大学院修了後、日本に帰国して就職することに決めた。
「そのときからすでに、私たち同性カップルの選択肢は限られていると思い知らされました。異性のカップルだったら配偶者ビザがあるから、いろいろな未来を考えられる。でも私たちはそれぞれが自力でビザを取るという大変な選択肢しかなかった」
それからふたりは1年半、アメリカと日本、遠距離で交際を続けた。
「でも日米の時差は大きな壁だった。関係を続けていくには、アメリカを離れて日本で康平と住む選択をしないといけないと思った」
アメリカで博士号を取るには通常7年ほどかかる。アンドリューさんは博士になる将来をあきらめ、日本に留学することを決めた。
「思い返せばそのころから選択を強いられ続けてきた。キャリアを取るか、康平と離れ離れになるか。常に将来を秤にかけなければならなかった」
2010年1月、康平さんと暮らすためにアメリカを離れたアンドリューさんだったが、2012年に留学ビザが終了した後、日本で暮らすための手続きも苦労の連続だった。
「私は2014年からフリーランスで仕事を続けて自費で滞在費用をスポンサーする扱いのビザに切り替え、『投資・経営(現在の「経営・管理」)』の在留資格となりました。煩雑な手続きが必要でした」
「異性婚だったらこんな大変な思いはしなくて済むのにと、ずっと思っていました」
アンドリューさんは振り返る。

同性カップルへの差別である
そもそも異性カップルで一方が外国籍の場合、その人は配偶者ビザによって容易に日本に滞在することができる。
さらには同性カップルの場合であっても、外国籍同士の場合は「特定活動」というビザが下りることが当時の出入国在留管理局の通知で認められている。
2022年9月、アンドリューさんに対するビザの運用は少なくとも後者の運用と比べて差別的取り扱いだという一審判決が出た後も、半年ほどの間、アンドリューさんへの特定活動ビザの発給は認められなかった。
「判決でも憲法違反と指摘されていたのに黙殺するなんて、なんて国だとそのときは思いました」、康平さんは振り返る。
2023年3月になりやっとアンドリューさんに「特定活動」ビザが下りた。しかしこのビザはあくまで一時的な「活動」に基づいた資格である。アンドリューさんにも週28時間までという就業制限がある。
そのためアンドリューさんは、就業の制限もなく永住権も取りやすい「定住者」ビザの取得を求めている。日本や日本に定着して暮らす人とのつながりを認められた人に対するビザであり、日本人と結婚し離婚した後の異性カップルの一方の外国人にも認められている。
「異性間の婚姻の相手と同性婚の相手で区別する合理的理由はない」——控訴審で提出された木村草太教授の意見書は、「日本人の配偶者としての身分を有する者の活動の本質は『共同生活』であり、『日本人配偶者と生殖関係を営む活動』ではない」として、「生殖関係の有無」で在留資格付与の取り扱いを変える運用は「法の下の平等を定める憲法14条1項に違反する」と指摘する。
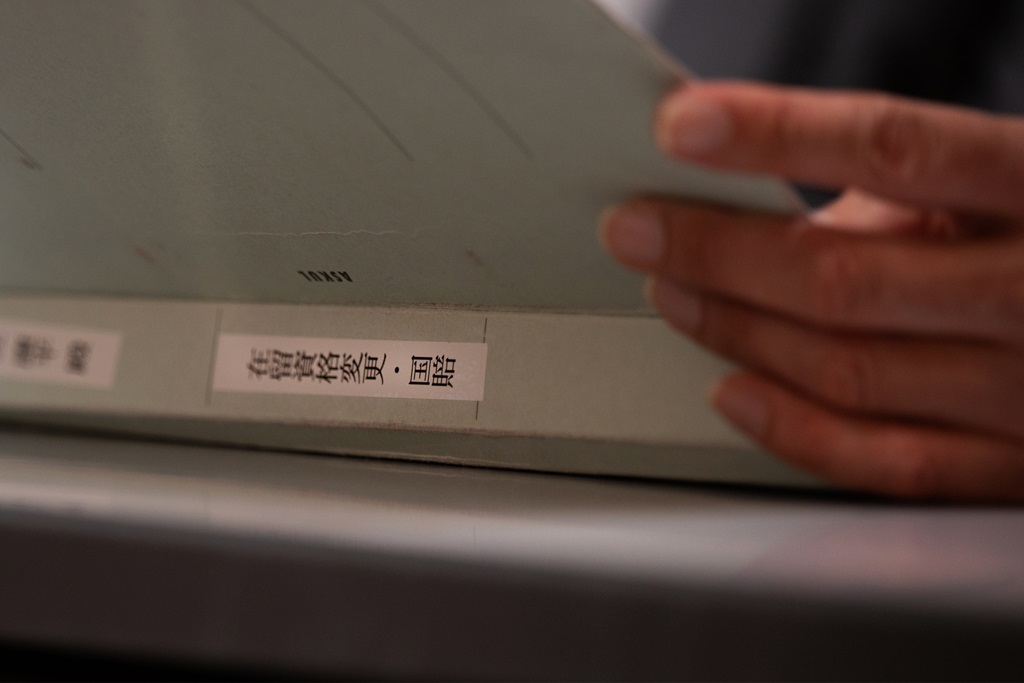
家族としての将来設計ができない
2015年、アメリカで同性婚が法制化した後、ふたりは渡米し法的に結婚した。しかし晴れて法的なふうふとなって日本に帰り、家族生活を続けようとしたふたりを待っていたのは、アンドリューさんの業務の終了とそれに伴う「投資・経営」ビザの終了見込みだった。
「投資・経営のビザだと、無収入でいられる期間が限られている。その間にこのビザでできる仕事を作らないとタイムアップです」
「私はソフトウェアの開発をしたかったのですが、日本ではプログラミングはアメリカと違う言語で行われていて、学ぶのに6カ月くらいかかる。そんな時間は与えられませんでした」
「結局、常に滞在期間が切れるかも、という恐怖に追われていると、長期的な目線でのビジネスの決断ができないんです」
「普通の異性の夫婦なら、どちらかが常にお金を稼いでいたり、学校に通っていたりすることは強制されないですよね。片方が仕事をしなくても、配偶者として扱われる」
「私たちだって普通のふうふです。それなのに、異性の夫婦だと普通に考えられる将来設計ができない。それは家族が引き裂かれることを意味します」
就業制限や長期的な目線でのビジネスの決断ができないという経済的不利益だけではない。いつ離れ離れになるか分からないという「法的立場の脆弱性」が、既に具現化している。
「異性婚の夫婦が当たり前にできていることができないと思うと、劣っていると言われているようでつらい」
そうつぶやくアンドリューさんは「国に帰れ」と言われることがあるという。康平さんも、「一緒に暮らしたいならアメリカに移住できるじゃん」と言われることがある。
「私たちは、いつ追い出されるか分からない恐怖の中、心を傷つけられ、精神的に追い込まれている。これは異性婚であれば起こらない問題ですし、国際カップルでなければ遭遇しなかった不利益。20年の時間をともにしていてもこの国で婚姻していないと他人と扱われる制度の問題であり、在留資格の取得すらままならない、運用の問題です」

家族生活をはばむ、外国人の人権の軽視
これは外国人の人権の軽視でもあるとふたりは主張する。
「そもそも家族を形成し、家庭生活を維持する権利は重要な人格権で、憲法13条の幸福追求権の保障のもとにあるもので、それは外国人であっても変わりない。国際人権法でも『家族生活の尊重』が権利として保障されている」
控訴審で出された曽我部真裕教授の意見書でも、アンドリューさんに在留資格を認めないことは憲法13条で認められる「親密な人的結合の自由」を制約し、国際人権法に反すると指摘されている。
「アメリカでアフリカ系アメリカ人に『国に帰れ』と言うのは明らかな人種差別(racism)だと、今では誰しも分かっています。では日本に住む外国人に『国に帰れ』というのは許されていいのか? これだって国籍による差別です」
「同時に、康平がゲイであることによって『外国人のパートナーと一緒に暮らす権利を制限されてもいい』とされていることは、性別や性的指向による差別(sexism)の一種です」

これは日本人の人権の軽視でもある
2018年、それまでの経営ビザでの滞在期間終了を目前に、ふたりは「家族生活を維持する」ため、さまざまな方法を試みた。5度のビザの申請のほかにも、国会議員や自治体の議員にアドボカシーもした。それでも、アンドリューさんに付与されるビザは最大90日という短期滞在ビザにすぎず、アンドリューさんは不許可却下処分が出るたびに不安定な立場に追いやられた。
「最後の手段である行政訴訟をするしかなかった」
「私たちにとっては、日本で一緒に暮らせるかどうかの瀬戸際の、緊急の問題だった」とふたりは声を合わせる。
「そして単に滞在許可を求めるだけでなく、同時に私たちの権利―平等権や家族生活を送る権利―も見える形で認めてもらうことが必要だと考えました」
「こうして私がアンドリューとともに国相手の訴訟を起こしたのは、これは外国人のアンドリューだけの問題ではなくて、自分のこと、日本人の問題でもあると思ったから。日本人として安定した家族生活を送る権利を奪われ、不平等にさらされていると思ったからです」
康平さんは提訴時のことを振り返る。
「私たちのような日本人と外国人の同性カップルは、家族生活をあきらめるか日本を出るか、強制的に選択する立場に置かれています」
「そしてそういう立場に置かれている人は、私たちのほかにもたくさんいる」
これは家族の問題だと、康平さんは言う。
「訴訟は最終手段だと思っていました。でも私は今日本で安定した仕事に就いているし、幸い声を上げることができる余裕があった。そうでなくて訴訟もできないたくさんの国際同性カップルがいる。日本を去らざるを得なかった人もいる」
「その人たちの分も含めて、私は日本人として、アンドリューと一緒に声を上げました」

訴訟の行方と求める変化
「一審の東京地方裁判所は『特定活動』の資格すら付与しなかったことは法の下の平等(憲法14条)に違反すると判示して、それは嬉しかった。でも本当の平等は達成されていない。外国人同士の同性婚カップルに認められている特定活動までは認められても、定住者資格は認められないし、異性婚のカップルと同じように配偶者としてのビザも与えられないからです」
康平さんは続ける。
「ゲイカップルだからとか、外国人と日本人の同性カップルだから移住しても仕方ないよねという風な考え方ではなく、ゲイカップルにも、国際カップルにも平等な法的手当が必要です」
「ですから私たちの訴訟はまだ続きます」
「けれど、今までの4年間、訴訟を通じて希望もあると分かった。まわりのサポートを受けることができて、支えてくれる人がいるのだということに気がつきました。
似た状況のカップルから連絡が来るし、レズビアンカップルの方でこの訴訟のホームページを作って広報を担ってくれるなど、ずっと支えになってくれているおふたりもいて、そういうことは本当にうれしかった」
「今回の訴訟を通じて、同性の国際カップルに対する運用の平等が認められて、似たような状況にあるカップルとか、日本を去らなければならなかったカップルも家族で戻ってきて安心して住めるようになってほしいと思います」

家族とは何か
「ほかにも未来に希望はあると思ったのは、高校生向けの課外授業で話をしたときのことです。私たちが在留資格の制限や、安定的な家族生活を困難にする制度的な差別について話すと、10代の若者たちが、それはおかしい、意味わからないですねと口々に言ってくれた」
「だからその子たちが大人になった後の将来には希望はあると思っています。同性婚の制度もできるかもしれない。ただ、自分たちには、『今』、『家族』としての関係性に基づくビザが必要なのも事実です」
そう話す康平さんの傍らで、アンドリューさんも言う。
「裁判所には、理論的にどうだという話からではなく、まず家族生活がいつ引き裂かれるか分からずに苦しんでいる私たちのケースにきちんと目を向けてほしいと思います。結局、国の制度の問題が、『国に帰れば』『アメリカに移住すれば』というような一般の人の差別意識を助長していることにも気づいてほしい」
話も終わりに差し掛かったころ、おとなしくしていたリラがまた吠え始めた。ふたりは「リラー……」と苦笑しながら、すこし照明を落とした部屋の中をせわしなく走り回るリラを見つめる。空になったアイスティーのグラスが汗をかいている。
ふたりが生まれたばかりのリラを家に迎えたのは2020年、訴訟を起こした後だった。「まだ小さいから、こうやって甘えて吠えたりするんですよね」と、康平さんがふたりと一匹の暮らしを話してくれる。
家族の根幹は「共同生活」にある。家族を言い表すことができるなら、それは人見知りの子犬と冷房の効いた書斎と、来客時のふたりの細やかな気づかいであり、それが全部合わさって醸成されたふたりのマンションの穏やかな空気であり、それは決して同性婚であることによって、国際カップルであることによって貶められるものではない。
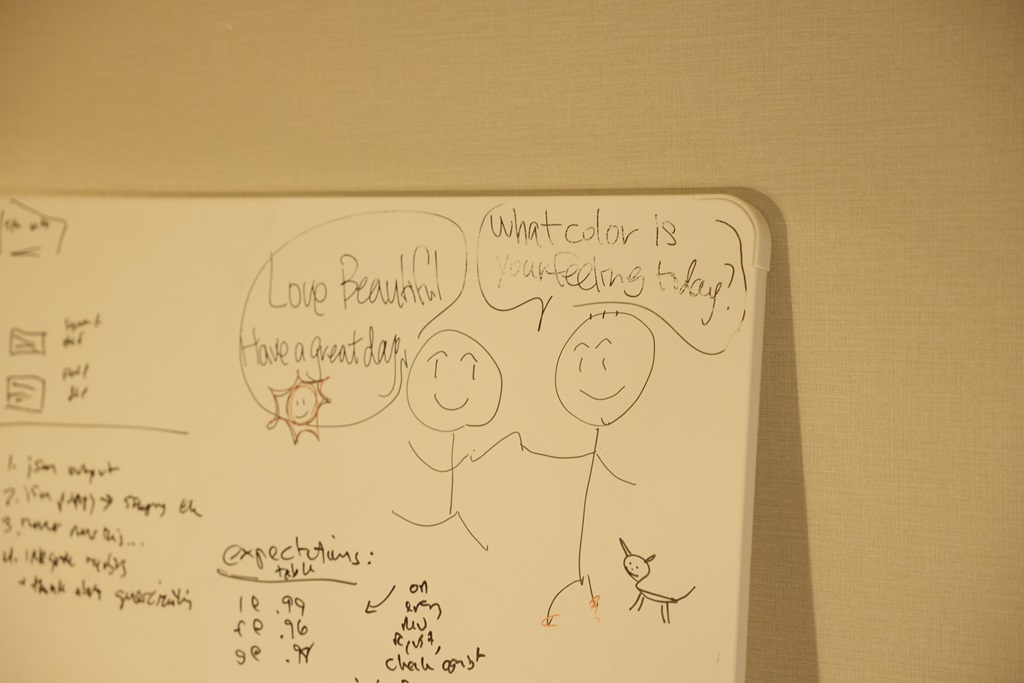
取材・文/原口侑子(Yuko Haraguchi)
撮影/鮫島亜希子(Akiko Sameshima)
編集/丸山央里絵(Orie Maruyama)
