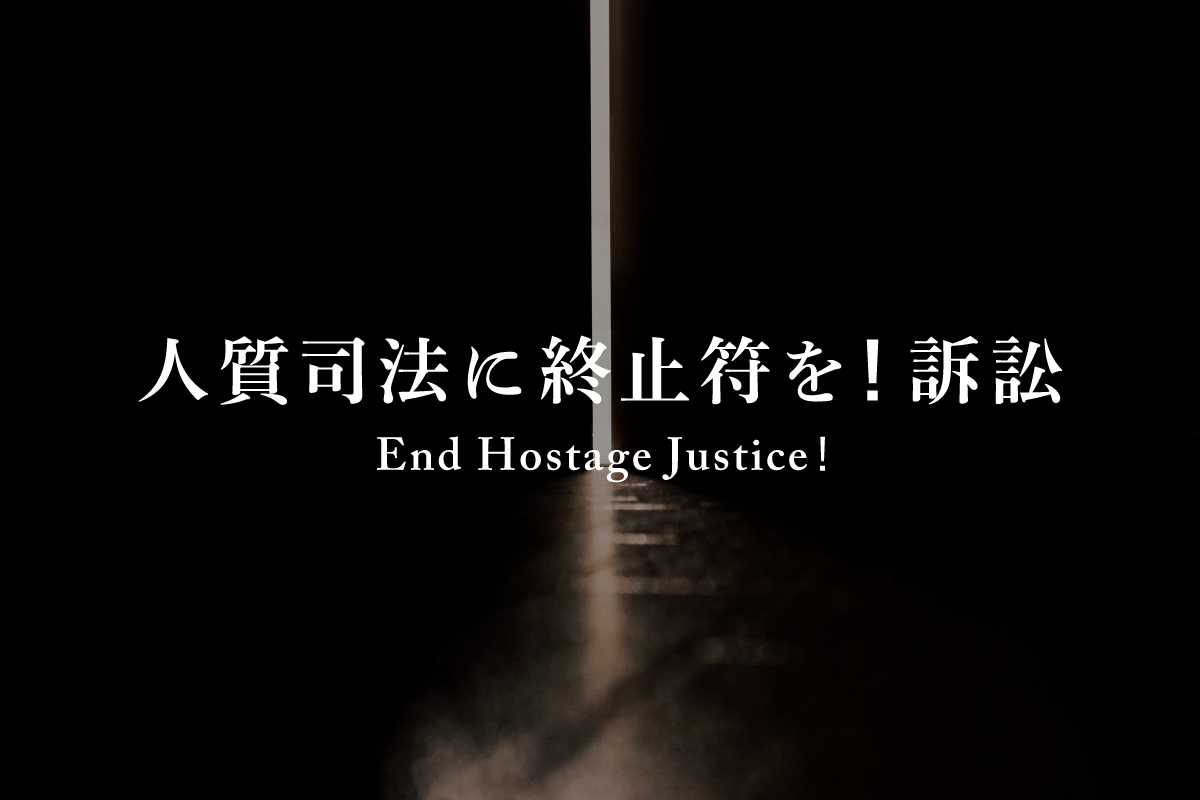初回期日レポート 「人質司法に終止符を!訴訟」

今年3月に提起された「人質司法に終止符を!訴訟」の第1回期日が、7月9日、東京地裁で行われました。原告の意見陳述から「人質司法」の厳しい現実が伝わってきた期日の模様と、その後に行われた報告会、そしてパネルディスカッションについてレポートします。
着席できないほどの傍聴人。関心の高さがうかがえる第1回期日
現在の日本では、罪を認めない人については、証拠を隠したり、逃げたりなどする可能性があることを理由に、逮捕後の勾留が認められたり、起訴後も保釈が認められなかったりして、結果として長期間にわたって身体拘束されてしまう運用がなされています。身体の拘束は究極の人権制約であるにもかかわらず、否認や黙秘をしているだけで、身体の自由が簡単に奪われてしまっているのです。そんな「人質司法」を終わらせるべく、「人質司法に終止符を!」訴訟が提起されました。
第1回期日が行われる626号法廷には、傍聴を希望するたくさんの人たちが足を運び、開廷時には着席できない人がいるほどでした。希望するすべての人が傍聴できなかったのは残念でしたが、それだけこの訴訟が関心を集めていることの現れでもありました。また、次回期日は東京地裁でもっとも大きい103号法廷で開かれることになりました。
証拠や答弁書の提出後、まず、弁護団長の高野 隆弁護士が訴状などに関する陳述を行いました。「80年前、この国は戦争に負けました」という印象的な一文から始まると、戦後公布された憲法には刑事手続きに関する人権規定を定められていること、そして1948年に公布された現行の刑事訴訟法では勾留はあくまで例外的なものとされていたことなど、被告人の権利を守ろうとしてきた戦後の歩みを述べました。
それが、80年近くを経た現在では真逆の状態になり、「人質司法」がまかり通っています。「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」という条文の文言は、誰が見ても罪証隠滅をするに違いない、その要件を言語化する修正案として提案されたものと説明をしたうえで、高野弁護士は続けました。
「実際には全く逆です。この文言によって、否認している被告人は勾留され、いつまでも保釈が認められません。逆に、自白した被告人は、すぐさま保釈されます。つまり、この条文は、実質的には、自白を強要する文言として機能しています」
どうしてこんなことになってしまったのか。高野弁護士の陳述に耳を傾けていると、「人質司法」が容認されてしまっているまかり通っている現在の状況が不思議でなりませんでした。
最後に高野弁護士は、正面にいる裁判長らに向かって強く訴えかけました。
「裁判長、そして両陪席裁判官、まずこの現状を理解してください。知ってください。そしてそのうえで、この国の刑事司法が、80年前の人々、憲法を制定した人々、新しい刑訴法を議論し制定した人々、その意図どおりに、そして、文明国の基準に則ったものに改善する、その道筋を我々に与えてください」

原告の言葉から伝わる「人質司法」の恐ろしさ
それから、4人の原告による意見陳述が行われました。最初の陳述は、天野さんです。天野さんは裁判中で、2018年11月に逮捕されて以来、6年以上勾留が続いており、この日も出廷がかなわなかったため、弁護士が代読しました。
逮捕前、天野さんは会社やレストランを経営していましたが、すべて閉鎖せざるをえず、収入はゼロになりました。「全身全霊をかけてやっていた事業を失った気持ちは言葉にすることが難しいです」と、たくさんのものを失った痛みを吐露しました。勾留中に家族や友人が亡くなっても葬儀に出席できず、劣悪な環境と粗末な食事で逮捕からわずか2ヶ月で体重が約25kg減少したという、心身ともに過酷な環境に、天野さんは現在も閉じ込められたままです。
受刑中の柴田さんの陳述も、弁護士によって代読されました。東京拘置所での2年以上にも及ぶ勾留中は、受刑中の現在とは比べられないくらい苦しく、「当時の暮らしは、箱に閉じ込められている状態です。しゃべることもできず、動くこともできないまま段ボールに入れられている、そんな感じでした」と振り返ります。
「未決勾留には終わりが見えず、絶望しか感じられなくなります」という柴田さんの言葉どおり、この瞬間も、未決勾留中で絶望に打ちひしがれている人がいることでしょう。そんな「人質司法」に一石を投じるために、柴田さんは原告となったのです。
次に盛本さんは、歩み出て裁判長の前に立つと、「人質司法」への怒りと、勾留中の過酷な経験、そして失われた時間への絶望感を、少し緊張した様子で語りました。「やってもいないのに、罪を認めてしまった方が楽なのではないかと何度も思いました」との言葉に、その過酷さが現れています。
「推定無罪の原則がどれほど重要かを、私は今、強く感じています。無実の人々が司法によって傷つけられ、時には人生を狂わせられる。その現実を目の当たりにし、私は何よりもその改善を求める気持ちが強くなりました」と、訴訟への思いを語りました。
最後に陳述したのは、看護師の浅沼さんです。トランスジェンダーであることから性自認などに関する執拗な質問を受け、「排泄や⼊浴の場⾯では、トランスジェンダーである私に対する無配慮な視線や対応が繰り返され、⼼⾝ともに深い屈辱と苦痛を味わいました」と、おそらく思い出したくもないであろうことを伝えました。
「誰もが、たとえ罪に問われたとしても、⼈権を持った⼀⼈の⼈間として扱われるべきです」という言葉は、そんな当然のことが守られなかった経験をした浅沼さんの心からの願いでしょう。誰ひとりとして、そんな扱いを受けてはならないはずなのです。
突然逮捕され、そのまま独房に勾留され、弁護士以外との接見を禁止されるなど、「人質司法」がどういったものかを情報として知る機会はあっても、実際に経験した原告の声で事実を耳にすると、改めて「人質司法」の残酷さが伝わってきました。
「人質司法」をなくしたいと声をあげた4人の原告の皆さんがいるからこそ、この訴訟は成り立っています。勾留中はずっと独りだった原告の皆さんを、今後の訴訟では決して孤独にさせないよう、たくさんの人たちと訴訟の行方を見守っていきたいと感じました。

訴訟が続くことで、「人質司法」の事実を明らかにする
期日後、日比谷コンベンションホールに会場を移し、期日報告会とパネルディスカッションが行われました。報告会では、事務局長の宮村弁護士からこの訴訟について改めて説明があり、第1回期日の報告、さらに今後の展開についても語られました。
さらに、国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表の土井香苗弁護士をモデレーターに、高野弁護団長と、人質司法の違憲性を問う「角川人質司法違憲訴訟」を提起している角川歴彦さん、そして原告の浅沼さんが、「人質司法」についてディスカッションしました。
勾留中に受けてきたことは、精神的な拷問だと語る角川さん。家族とのコミュニケーションも絶たれ、助けてほしいという声をあげることさえできなかったという浅沼さん。このような人権侵害がなぜなくならないのでしょうか。
角川さんが言及したのは、「人質司法」はシステム化されており、検察官としてもマニュアルに従うしかないという、この問題の根の深さです。けれども、角川さん自身の訴訟に続いて、「人質司法に終止符を!訴訟」があり、さらにこの後も訴訟が続いていくことで事態が明らかになっていくのでは、という希望が感じられる話も出ました。
「人質司法に終止符を!訴訟」は、始まったばかりです。自由主義国家では日本だけとも言われる「人質司法」を終わらせるべく、ぜひご関心をお寄せください。第2回期日は、9月24日午前11時から、東京地裁103号法廷で行われます。ひとりでも多くの皆さまに足を運んでいただければと思います。